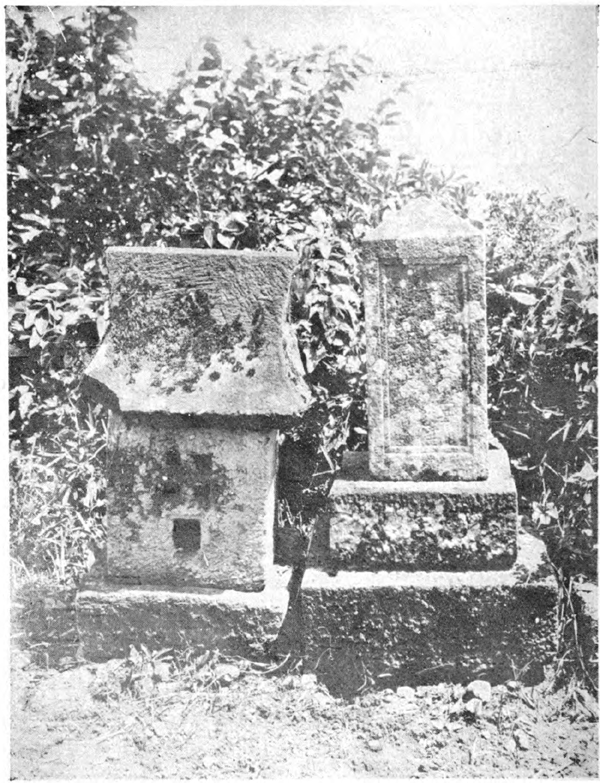
目次
加沢記の成立
「加沢記」は沼田真田藩第五代藩主、真田伊賀守信直(信利)の時代から、天和元(1681)年に改易される後までを費やし完成を見た。内容は、上野国吾妻・利根両郡を支配した真田家を中心に、戦国時代初期より武田家において台頭した真田幸綱(幸隆)に始まり昌幸、信幸(信之)の時代までの事象を吾妻郡の動向、利根郡の沼田氏、群馬郡白井城の白井長尾氏の記述など詳しく述べている。平次左衛門は江戸初、中期の人物なので、実際の戦闘の経験は無かったでしょう。恐らくは、戦闘を経験した古老の話や資料を集めまた、自分の足で現地を調査して書き上げたものであると思います。
加沢平次左衛門
加沢氏の出自は、信濃国小県郡県村賀沢である。その地は真田氏と同族の海野、祢津、矢澤氏の本貫地と接している。賀沢氏はそこから発祥し、終始海野、真田氏に仕え戦国時代吾妻、利根に移ってきたと思われる。元々は、沼田真田藩の家老の祢津氏が主筋となるようだ。中之条町伊勢町、一場氏の子孫の家の「親類書之覚」という記録を見ると平次左衛門のことが記されている。これによると一場茂右衛門の母と平次左衛門が兄弟であったことが分かる。没年は、元禄7(1694)年である。この平次左衛門は、中之条町平の小林家(現矢澤家)より加沢家に夫婦養子となっている。この小林家と加沢家は、縁戚であったのでしょう。そして、一場家と小林家、加沢家は女系でつながる親戚である。加沢家は、信濃より吾妻利根に真田と共に来て吾妻、利根の郷士と関係を持ちつつ沼田真田藩士として地位を確立していったようである。加沢平次左衛門の墓は、利根郡上川田にあるが、吾妻郡中之条町平の矢澤家の墓にも真田昌幸、矢沢綱頼の供養塔と共に加沢平次左衛門の供養塔も存在している。
<参考文献:新釈加沢記 加沢記釈文 加沢記附羽尾記>
「加沢記附羽尾記」グーグルブックのリンク(下リンクをクリック)
https://play.google.com/store/search?q=%E5%8A%A0%E6%B2%A2%E8%A8%98&c=books
巻之一
滋野姓海野氏御系図附けたり真田御家傳之事
海野氏は清和天皇(第五十六代)の第五皇子貞元親皇より出た滋野氏を基にしている。正平年間貞元親皇は勅命を受けて関東に下るが、そのとき滋野の姓を戴き、信濃の国司に任命された。その位は四品、治部卿である。信濃の赴いた滋野氏は小県郡海野の勝に住む。法名を関善寺殿と言い、真言宗秘密の道場を建立している。そして海野家では毎年四月と八月の四日を「白鳥」と呼んで祭りをしている。新皇には男の子が一人有り、海野小太郎滋野朝臣幸恒と命名されて海野氏が始まる。ある時幸恒は三人のわが子を連れ、武石山中に狩りに出かけた。そして千曲川のほとりに立って、領地を三人に分けた。長男を海野小太郎幸明、二男祢津小次郎真宗、三男を望月三郎重俊といった。法名を長男から前山寺殿、長命寺殿、安元寺と呼ばれ、それぞれ真言宗の僧を招いて寺院を建てている。
その後の幸明の系図を見ると、孫が幸盛でその弟が下屋将監幸房である。この人は吾妻郡三原という所に住んで、鎌原、西窪、羽尾の三氏を出している。太郎幸盛の方は玄孫が海野信濃守幸親とその弟海野弥四郎幸広で、二人は寿永二年に木曾左馬頭義仲の幕下には入り、平家追討の宣旨受けると備中国水島に駆けつけ、追手の大将を承るが、その年閏十月一日に戦死している。その功により嫡男は左衛門尉を襲名して海野幸氏となる。
その子が信濃守幸継(中善寺殿)で、六人の子があり上から海野小太郎幸春、会田小次郎幸元、塔原三郎氏広、田沢四郎氏勝、狩谷原氏重、光六郎氏頼と名乗る。この六人はいずれも信州で地頭となっている。また刈谷原に三子あって、氏治、氏陸、氏截と言う。
長男幸春からずっと下って十一代に兵庫守幸則があり、その長男が幸義、二男が岩下豊後守と言う。幸義三世の小太郎は、鎌倉公方足利持氏公から生前の名の一時をもらい持幸となる。
持幸から三代の地に海野小太郎棟綱が現れる。この頃になると都も地方も不穏で、どこも兵乱が絶えない有り様となる。そこで棟綱は小県郡砥石と上田原に城郭を築く。棟綱には四人の子があり、長男は海野左京大夫幸義、二男を真田弾正忠幸隆、三男を矢沢右馬介綱隆(後の薩摩守頼綱)、四男を常田出羽守俊綱(武石右京進)と名乗る。棟綱は領地を譲るが、二男幸隆には真田、小日向、横沢、原の郷、荒井在家三百貫文の土地を配分し、臣下には矢野、川原付けて与えた。幸隆は武運長久と子孫繁栄の吉相が見えていた。まず真田村に甲田と言う家並みを整えている。甲田はこの郷の鎮守、白山台権現が鎮座する地であった。
ここで白山大権現の縁起というのは、我が国の元祖にあたる伊弉諾尊をご神体として、これを白山大権現と言って敬ったのである。
これは信州浅間山、吾妻屋山の権現と一体をなす物である。真田の白山は信州の鎮守の里宮で、上州では吾妻郡三原の郷に同じ里宮がある。その二つとも幸隆の祖先貞元親皇が建立した物と伝えられている。幸隆はこの地を領有すると、鎮守をあがめ、自分は由緒のある家名を相続したことを名乗ってから末の繁栄が約束された。
幸隆には五人の子があり、長男は真田源五郎であり、後源太左衛門信綱となり二男は兵部介信貞(昌輝)、三男を喜兵衛尉昌幸、四男が隠岐守昌君と名乗った。幸隆は文武両道に勝れていた。当時、公方は義□公の時代で、公方の命令に従う物もなく、国々は兵乱の時代となっていたおりである。幸隆は所々の城に攻めかけ、合戦には勝利を収めないことはなかった。
其の頃、信濃国では、数多くの地頭が支配していたが、なかでも村上義清や木曾義昌、諏訪頼重、小笠原長棟らは、かの国の頭領で、彼ら四大将は領地争いを続け、大身は小身をかすめ取り、小身は細工を労して他の領地を奪おうと、戦を挑むようなときであったので、滋野の一族はあげて村上殿の幕下に降伏し、人質を渡しておいた。
<解説>
真田氏の祖滋野氏は、清和天皇の第五皇子貞元親皇が信濃守に任官し、任地に下って天皇より滋野の姓を賜ったと「加澤記」にあるが、おそらく遙任と言って任地には赴任せず、都に残ったまま任官したのではないのかと思います。上野国も新皇の任官することが多かった国で、やはり「遙任」上野介(国守の次官)が現地に代理として下っていたように信濃国も同じだったと思います。また、新皇が賜る氏は源氏、平氏など武家として有名な氏ですが、新皇が臣籍降下するときに賜る氏がいくつかあり「源」「平」などもそうであり、「滋野」もその一つだったのでしょう。その滋野の一族が、都より下り小県郡の開発領主として土着していったのでしょう。
真田氏は滋野氏の出であると唱えている。松代真田藩の真田伊豆守信之は、「真田伊豆守 滋野信之」と名乗っていました。「加澤記」においては、滋野の直系海野棟綱の二男としているが、真田氏は中世から存在していたようである。真田幸隆は「弾正忠」を名乗っていたが、これは正式に名乗ったわけではなく箔を付けるために勝手に名乗っていたため正式に任官したわけではない。幸隆の通称は源太左衛門と言っていた。
真田氏は海野の嫡流を名乗っているが実は幸隆は真田頼昌の長男として生まれて、真田源太左右衛門幸綱といったと今では定説となっている。母は、海野棟綱の娘だといわれていて、海野棟綱の母系の甥にあたる。また、幸綱の弟は祢津系の矢沢家を継ぎ矢沢源之助綱頼と名乗り、後真田家の有力な家臣となっている。兄弟とも「綱」の字が共通していて、おそらく海野棟綱の「綱」の諱をもらった物と思われる。通称には「源」の字が共通していて、これは真田家の共通する字だったのでしょう。幸綱の長男信綱(長篠の戦いで戦死)も源太左右衛門を名乗っているところから、真田家の惣領の通称だったと思われます。
関東の動乱「結城合戦」の従軍者のなかに「実田」という者が見える。当時の文書には当て字が多かったので、「実田」は「真田」だと思われるので幸隆はこの文書にある「実田」の子孫であったのでしょう。もちろん、滋野一族であることは代わりありませんが。幸隆の弟が祢津家の一族「矢沢」を継いでいるところから、真田氏は祢津の分れではないのかという説もあります(矢澤系図)。
真田の祖「源太左衛門幸隆」は五百貫文の領地といわれていますが、この領地は江戸時代の石高に換算しますと、信之が松代に移封されたとき一貫文3石と言われていますので3石として1500石前後の領地だったでしょう。兵力にすると五十人程度、多くても百人に満たない程度の徴兵能力だったでしょうから、滋野一族すべて合わせた数も五百人~八百人程度の勢力だったと推定されます。信濃が、一国を統一するような大勢力がなかったといっても北信の雄、村上氏とは敵対していたがはるかに村上氏の勢力が勝っていました。
真田右馬介綱吉
永禄8(1541)年8月、武田信玄は家臣団に対して生島足島神社起請文を提出させている(参考:起請文にみる信玄武将)。この中に海野衆として、12名の連名の起請文に真田右馬助綱吉の名が見える。はて、この人はいかなる人物であろうか。広く知られている、真田幸隆(幸綱)の系図からはその名は出てこない。そもそも○○衆というのは、ある特定の地域の小領主がまとまって集団を作り、戦国大名に対して国衆と同じ発言権や軍役をこなす者である。海野氏関係の中では海野幸貞が単独で、幸忠、信守が2名連名で、そしてこの綱吉が12名連名の中に名を連ねている。これを見ると、幸貞が国人領主、幸忠、信守が準国人領主、真田右馬助綱吉を含む12名は、郷士連合というような位置づけになるのか。
この、真田右馬助綱吉なる人物が真田弾正忠幸隆(幸綱)の兄、つまり近年の説で、幸綱の父と言われる真田右馬助頼昌の嫡男ではないかと言われ始めている。これは、東御市の深井家に伝わる文書などから「真田右馬亮綱吉」法名「嘉泉院眞相勧喜大禅定門」である。この人は、東部興善寺と高野山蓮華定院で元和9(1623)年庄村金右衛門によって供養されたと記録されている。
深井家の過去帳によると、「真田馬之亮綱吉」の子は
「真田馬之亮綱重」で法名「深井院寛誉宗眞居士」とある。
この深井綱吉は真田右馬助綱吉であり、深井郷が本貫地であったのは間違いないようである。家紋は、六文銭である。
以上の事例と、真田幸隆(幸綱)の武田家における信州先方衆以前の事象が分からない点など踏まえると。真田幸隆は、真田の嫡流ではなかった(もちろん海野の嫡流ではない)と捉える説が有力になる。そうするとこの深井(真田右馬助綱吉)綱吉という人物、真田頼昌から続く嫡流は綱吉につながる系統ではないかと感じさせるのである。
昌幸に関しても、真田家の正統後継者ではなかったという説もある。
ただ、真田一族の中で弾正忠幸隆(幸綱)が武田家において一番勢力があった人で、出世頭だったのはまちがいの無い事実であると思います。この事例は、今後の諸先生の研究に期待したいと思います。
祢津宮内太輔覚直の一族に大塚掃部介幸実という人が居た。元を正せば祢津とは同族借谷源五郎の子孫で、そのとき水内郡大塚で地頭だった。幸実は村上頼平の頃から無二の村上の幕下であった。その年諏訪大社の参籠しては諏訪頼重に対面するなどの行動により、村上義清に怪しまれて、領地を没収されてしまった。
幸実は小県郡に身を引いて浪人となる。これを見て村上義清は、この際滋野一族を退治しようとする。覚直はこれを聞いて、事態は容易ではないと村上方に先手攻撃をかける。まず葛尾を攻めることとなるが、海野幸象が惣領家にあたるのでこの事情を説明した。幸象は使いのおもむきを聞いて、「絶好の機会である。近年村上に横取りされて無念に思っていたが、どうしようもなく無力で是非もなかった。今こそ我にとっても好都合、舎弟幸隆は知謀の勇姿であるから意見を戴くこともできよう。」と、小草野孫右衛門を真田にやる。幸隆は上田まで出る。-そこに矢沢右馬介殿も来て、一族みんなで話し合った。
天文十年二月下旬のことである。右京大夫幸義、宮内太輔覚直舎弟美濃守信直は二手に分かれ、先陣は弾正忠幸隆、本陣と前備矢沢右馬介、鞠子藤八郎、村上土佐守、後陣は小泉常田と定め、六連銭の朽葉四方の大旗に州浜の紋章、白地に日の丸を染めた大旗を真っ先に立てて進み、その勢力合わせて二千余騎が、葛尾へと押し寄せた。
一方義清のかねてからの用意の通り、高梨子信濃守を先陣に立て、石畳の紋を染めた大旗をかざして二千余騎の軍勢。義清は遙か後方に下がって進軍し、上田と榊の間に陣取ると、千曲川のほとりで備えを固めた。
前の備えは室賀八代の率いる一党千五百余騎、後ろ備えは大室、清野、望月、覚願寺、小笠原、西条、下条4、松尾、芋川らが、また麓の備えは綿内、食品、草間、寺尾、赤沢、波浮、雨ノ宮、座光寺、八幡社主らが、後方に下がって、小丸山の方に陣を敷く。その軍勢はおよそ二千余騎、都合五千四騎が轡を並べて静まり替えている。
先鋒幸隆は、敵陣丸山の状況について幸義に仰せになる。「村上方の備えを見れば、鶴が翼を広げたように兵を並べ、我が軍を包み込む配備を整えている。わが方の攻めをを待つように思われる。わが方が少しでもたじろぐようであれば、決って配備を崩し押し寄せるに相違ない。そのときはかねて山陰に隠しおく祢津の一勢で持て後を遮り、敵を討ち取ることができよう。我はそのときを見て、森の木陰から回り込み、義清の旗本へ攻め入り、有無勝負を決しよう。」と、軍法を定めあって備えをとき姿を消した。
すると案の定高梨子はひるがえる旗の動きに戦況有利と見て、ホラ貝を吹き立てたので、戦陣後陣の兵はこの合図に「おう」とときの声を上げ、もみにもんで攻め立ててきた。大将幸義は辛抱強い方ではない。程なく引き返すが、村上はまだ本備えを固めて動かない。こうして幸義が誤算に気づいたときはすでに遅く、その結果高梨子と戦う羽目と成、激しく交戦してひとまず高梨子を山上に追いやるが、そこに後陣に回っていた室賀八代が、新手を繰り出してさんざん攻め込んできた。
幸義の武運はそれまでであった。乗馬が堰溝に飛び込み、前膝を突き当てて倒れた。幸義は馬の後ろにどっと落ち、起き上がろうとしたが、多勢に重なり合って槍ぶすまを突き当てられ、脇下から乳のあたりを突き当てられた。
幸義はこれまでとてにした槍を投げ捨て、太刀を抜き室賀の家臣芋川に挑み、真っ二つに切り裂いた。この勢いに敵はたじろぎ寄る者もない。そのうち見方の軍勢が駆けつけて敵を甥は追おうとするが、勝ちに乗じた敵兵は槍を突いて攻め立てるので、とてもかなわない。
舎弟右馬介綱隆は、目の前で兄を討たれては末代の恥なりと高々と唱え、馬から飛び降り、海野重代小繋松の作と伝わる手槍をひっさげて立ち向かう。家臣の庄村、上原、山越、神尾も続いて、一気に攻めまくる。このとき綱隆は武勇無頼若者盛りであった。たちどころに付近の敵十三騎を打取って、気勢を上げたが、幸義はむなしく事切れていた。
それより民家から板戸を借りてきて、春原惣右衛門、川原惣兵衛両人が遺体をかばって落ち延びた。
一方山陰に隠れていた宮内太輔は、見方が敗れていた様子を見て幸隆に合流すると、一気に義清の本陣に押し寄せる。そこで幸義戦死の報を受けたのである。我ら生き残っては末代までの名折れと覚直は祢津相伝の橋返りの太刀を抜き払い、幸隆は、棟綱公より賜った三尺五寸もある厳物造りの太刀を真っ向からかざして、一文字に義清めがけて内かかっていく。
これをみて、別府、小林、三宅なども続いて攻め立てる。村上方は一時危うく見えた。部下覚願寺信清は義清を討たせてはなる物かと、かけてきて立ちふさがり、綿内、大室、食品らの五百騎もこれに加えて互いに火花を散らせたが、夕暮れともなってどちらとも引き上げた。その日の戦いは終わった。幸隆は味方の軍勢を集める。その損害は一千余騎が戦死、残った大半も傷を負っていた。
これは、海野平の合戦のことを書いていると思われます。滋野一族のもっていた海野平の地である滋野一族の領地を、村上義清はかねてからを狙っていてその機会を伺ってていたのでしょう。かねてから、北信の村上、高梨氏は領地争いを繰り返していたが、この頃和睦して村上氏の上田原侵攻の準備が整ったと思われます。しかしこの滋野一族の没落した戦は、史実では武田信虎(信玄の父)、諏訪頼重、村上義清の連合軍によって攻められて没落したようである。この記を書き残した加沢平次左衛門は沼田真田藩の藩士であり、真田氏のを誇張して書かなければならなかったでしょうから少し割り引いて考えた方がよいと思います。特に、真田幸綱(幸隆)については真田藩にとって元祖となる人物となるので、文武両道に勝れた名将という位置付けをしなければならなかったと思います。まあ、この真田幸綱(幸隆)については武田家の二十四神将の内に入っている人物なので名将には違いないとは思います。信憑性ということは、横に置いて海野氏没落の事が分かる記述だと私は思います。海野方の諸将の中には矢澤馬之亮、春原兄弟、祢津氏などは諏訪神社途の関係から許され地元に残り、海野棟綱や真田幸綱は上野国守護上杉憲政のもとに逃れます。上野守護で関東管領上杉氏は、信濃の一部にも領地がありましたのでそんなことが関係していたのでしょう。
真田氏の系譜諸研究の結果
真田氏の出自の見解は、「寛永諸家系図伝」がある。これは、松代真田藩の正式見解である。清和天皇の子、貞秀親王が滋野初代としている。貞秀親王の子、幸恒が初めて海野小太郎を称した事で海野の系譜が始まるとしている。幸経の弟、次男直家が禰津、三男重俊が望月を称した事で、滋野三家が始まる。
真田家については、幸隆(正しくは幸綱)が海野棟綱の孫、幸義の子としている。幸隆が真田荘に居住した事により海野から真田に改正したとする。しかしこの主張は、新井白石によって否定されている。まず、貞秀親王は存在しない事に疑問を持ち、白石が独自の論じている。延暦年間(782年~806年)、滋野東人の子尾張守家訳が滋野宿禰姓を賜り、弘仁14(823)年に家訳、貞主父子が滋野朝臣姓を賜ったと指摘したのである。貞主には二人の女子がおり、一人は本康親王を産み、もう一人は文徳天皇に嫁ぎ惟彦親王を産む。この惟彦親王は、清和天皇の兄に当たる。この両親王外戚としての繁栄を評価して、貞主を海野氏の祖と結論づけている。
また、前述の指摘を踏まえ真田家は「寛政重修諸家譜」の時清和天皇の第五皇子、貞保親王の孫善淵王が滋野姓を賜りこの人を祖としたのです。
しかし、最近の研究では貞観10(868)年から10年間信濃介なっていた滋野朝臣恒蔭、同12(870)年から4年間信濃守であった滋野朝臣善根に注目して、信濃滋野氏についての関係性を指摘している。そして、滋野惣領家は海野氏ではなく望月牧を管理していた望月氏ではなかったかと指摘している。(栗岩英治氏説)
「大日本史氏族誌」に於いて、伊蘇志臣東人の孫家訳とその子貞主が、桓武天皇の時滋野宿禰姓を賜り、嵯峨天皇の時滋野朝臣姓を賜っていて、海野氏はこの滋野朝臣貞主に始まるとしている。そして、滋野氏の中で信濃の官人となった人物として、滋野朝臣恒蔭、滋野朝臣善根、さらに天歴4(950)年頃、望月の牧官に任じられた滋野幸俊の存在も指摘している。(藤沢直枝氏説)
以後時系列にて、諸研究の論説を紹介したいと思います。
滋野氏の出自
飯島、黒坂両氏は、それまでの研究を整理した。滋野氏の出自は、奈良時代大学頭兼博士であった樽原東人であるという。東人は天平勝宝元年(749)駿河守就任時、産出した黄金を献上し称えられ伊蘇志臣の姓を賜った。東人の孫家訳が延暦17(798)年、滋野宿禰を賜り、さらに弘仁年間(810から823年)滋野朝臣を賜った。そもそも姓というのは天皇家から授かるもので、現代の姓は俗に言う字名のことである。たとえば、鎌倉から室町の初期にかけての吾妻の有名人、「吾妻太郎行盛」は正式に名乗るとまず字名と通り名を名乗る。次に姓と諱を名乗るのである。つまり正式名は、「吾妻太郎藤原行盛」である。ちなみに真田信之は、「真田伊豆守滋野信之」である。話を戻します。滋野家訳の子に貞主、貞雄がいた。特に貞主は学者、政治家として名をはせその娘綱子は仁明天皇の妃となり、本康親王を産み奥子は文徳天皇の妃となり、惟彦親王を産んだ。滋野氏は、天皇の縁戚となっていた。そして、滋野氏と信濃の関係は信濃守善根の存在を確認できる。滋野氏は清和天皇の子、貞秀親王の子の善淵王となっているがこれは信濃守善根の音の転化ではないかと指摘している。
黒坂氏は更に、善根を貞主の次男とし信濃介恒蔭を孫と推定した。当時は守は遙任と言って現地には行かず介、次官が現地に赴くことがよくあった。そして、滋野恒蔭は都の貴種であったので、現地豪族が娘をあてがって子供をなしその子を嫡子として出自をその貴種に求めるようなことが行われていた。群馬県吾妻郡東吾妻町にも、そのような伝説がある。日本武尊が東征のおり、この地の訪れた。そのとき原町上野の上野長者というものが娘を日本武尊にあてがい、子をなしたと伝わる物がある。地方豪族は、その子を嫡子とすることでその地方の支配を確立しようとしていた。この滋野三家も、恒蔭にその血筋を求めていたのかも知れない。ただし、滋野氏が清和天皇から出ているという説は、根拠を見いだせない。おそらく、信州の海野氏が滋野恒蔭が在任中にその出自の根拠を求めたのでしょう。これは、信州望月牧の支配を確立するための手段だったようにも思います。
真田氏の出自
「信州滋野三家系図」を見てみよう。これは真田家が幕府に提出した「寛政重修諸家譜」と清和天皇-貞秀親王-善淵王-海野初代と同じであるが、鎌倉初期の海野の当主長氏の四男に、真田七郎幸春という人物が見られる。其の祖父幸氏は、「吾妻鏡」に上州三原荘の地頭という記述が見られる。この系譜を見ると真田氏は、鎌倉時代初期に海野氏から別れた庶流と言うことが言える。次に応永7(1400)年大塔合戦(大塔物語)に「実田」という記述がある。この時は、禰津遠光の配下として出陣しているようだ。その後永享12(1440)年結城合戦の時、信濃守護小笠原政康、持長、村上頼清に率いられて真田源太、源五、源六という記述がある。これらを状況証拠と捉えると、真田氏は鎌倉の始めに滋野三家から別れた家であると言うことも言えると思います。また一説には、宝亀5(774)年に大伴連忍勝という人物が小県郡にいたという説もあり、真田氏の祖はこの末裔ではないかとも言われている。大伴氏は淳和天皇が名を大伴と言ったため、名前を変え伴氏となった。平安時代この判一族は、軍事を司る役人であった。そのため平安時代には、各地の官牧を管理する役人として赴任していた。そのため、真田氏は伴一族のではないかという説もある。それでは、戦国時代の海野系図を見てみましょう。白鳥神社に残る海野系図では真田幸隆は海野棟綱の娘の子、というふうに書かれている。もう一つは、矢澤家の菩提寺良泉寺に残る矢澤系図では、矢沢綱頼は真田右馬佐頼昌の三男としている。この事を見ると真田幸隆(幸綱)は頼昌嫡男と言うことになる。つまり、海野棟綱の娘婿のこと言うことである。しかし、白鳥神社に残る海野衆起請文の中に、真田右馬佐綱吉という人物が存在する。これを総合的に状況証拠と捉えると、頼昌と棟綱の娘の子で嫡男が綱吉、次男が幸綱(幸隆)、三男が綱頼(以下続く)となるわけである。そして、三人とも海野棟綱の綱の字を偏諱として名乗っているのである。真田幸綱(幸隆)は、海野棟綱の外孫であると考えてもよいようである。ただし、この頼昌の記述は良泉寺矢澤家系図のみである。この家系図の成立は、元禄9(1696)年であるのでこれが正解かと問われても疑問が残る。ただ、これが現在では通説となっている。ただ、幸綱(幸隆)と海野棟綱の娘が婚姻していたという説もある。ここでは、幸綱は海野棟綱の外孫と言うことにしておきます。
幸隆公武略を以て討ち給う事
幸隆公が常々心にかかるは、一度敵を討って幸義の供養をいたしたいと心に思い、武田に属し本領に復帰したけれど村上義清をそのままにしておくのは無念と思っていた。幸隆に二名の老臣有り、小草野若狭守と春原惣左衛門の兄弟は武勇知謀万人より勝れていた。幸隆兄弟を召し出し話した。「其の方先祖は武蔵国住人宣下天皇の末孫丹治姓で熊谷、青木、勅使河原、安保氏の丹党(武蔵七党)で、熊谷より別れた久下、熊谷、春原として兄弟三家に分かれた。世の中の浮き沈みにより、関東より当国に至り我らが先祖に属し、代々の家臣である。おのおの存知の通り、義清を討って左京太夫(幸義)殿のご供養を報じんと度々合戦に及ぶが、大名なれば中々討つ事ができず年月を重ねる事非常に無念である。兄弟の命を右京太夫殿の志に捧げてもらえまいかと問うと、我ら不肖と言えども代々の家臣である。その申し出にいかに逆らうべきもない。と申し上れば幸隆公大いに喜び、ならば手立てを持って討つべしと申された。春原兄弟はその後奉公も真面目にやらず、法度に背き、軍法を犯し適地に内通し、近国まで聞こえる悪逆を行った。幸隆公これに大変ご立腹なさり、一族ことごとく知行を没収し、追放した。
兄弟まず関東へ浪人して続いて信州川中島の村上義清に仕えた。義清は最初、信用しなかったのであるが大敵真田の様子を聞かんが為、そのまま仕えさせていた。また、惣左衛門は小男であったが国中に聞こえた勇士であったが故そのまま抱えていた。兄弟粉骨を尽くして尽くし、昼夜の勤めも諸人より勝れ村上でも一二の忠功の人にて同心、与力も預かるほど信用されるほどとなった。なほ以て忠勤に励んでいたところ、村上に密かに呼ばれて、「其の方の先主真田を討って安堵したいと思う。兄弟のはかりごとを以て討ちたいので、相談したい。」と言った。ついに、願うところ思ったが、胸騒ぎがして返答に困った。惣左衛門が言う「それがしは砥石山の生まれにて、旧友も多い。真田の内情については書状などで知っている。密かに白山権現に参拝して、戸石城の内通の謀をしてきましょう。」と明日を遅しと、ただ一人小県へと出かけていった。かねてからのたくらみごとなれば、夜中に丸山土佐、川原、矢野方に内通すれば幸隆大いに喜び密かに対面した。惣左衛門は夜中に立ち帰る。さて、惣左衛門葛尾に帰り申した。「白山に参拝し、城中への通路を調べようとしばし社中にとどまっていると、権現様の引き合わせかもと同輩川原惣兵衛というものが参詣してきた。川原と申す者は武州七党の内の一族で、共に先祖は信州に来た旧友であった。拝殿にて偶然行き会った。互いに懐かしく、打ち解けてお互い語り合ったのであるが惣兵衛が言うには、「其の方も代々の老臣であるが、少しの事で簡単に追放された。我らと手危うきものである。丸山、矢野、深井、宮下などいずれも今日限りの奉公である。明日にも浪人して、村上殿を頼みたい。其の方に万事頼みたい。かねてより義清公も「各各幕下に加わるのであれば、望みの所領を与えよう」と常々申していたので惣兵衛喜んで、二心はなく、我らも幸隆に恨みがあるので兵をお出し下され。「夜中に幸隆を城中におびき寄せ、安々と討ち取ります。」と弁舌爽やかに述べれば義清大いに喜び、日日を選んで春原が娘を人質に取り小草野若狭守、春原惣左衛門を案内者にして勇兵を選りすぐり七百騎を以て真田の城に攻め寄せた。
あらかじめ段取りの通り、戸石の木戸を開いて夜中に忍び入りにの丸にさしかかるとき、春原法螺貝を吹くとその先の門を閉じて弓、鉄砲にて物陰より攻撃を受け七百騎の兵の内五百騎が討ち取られた。残る百五十騎余りは、巳の刻逃れ落ちた。義清、春原兄弟を信用した事を後悔したが、もはや遅い事であった。春原兄弟の人質を牛裂きにしたが、五百騎の精鋭を討たれた義清はさすがに抗しがたく熊坂峠を経て、越後の景虎を頼り落ちて言った。これより残る領地を景虎に相渡し、春日山に居住する事となった。幸隆公の武略、春原兄弟の働き武田晴信公に聞こえ大いに喜ばれた。幸隆公に夫具不例の感状があり、春原兄弟も召し出されそれぞれ百貫文ずつあてがわれ、武田家直参となった。幸義公の御跡は、海野太郎と申して海野郷に小身ではあるが残っていた。永禄年中、義清越後に浪人して景虎を頼っていれば、毎年信州へ出陣していたが折しも海野これといった働きもなかったのを、晴信公お聞きにになり御誅伐した。しかし高家の跡なればと、晴信公のご実子御聖道という盲目におわすを海野殿になされ、春原が兄小草野若狭守を彼の陣代とした。
<解説>
天文二十(1551)年五月二十六日「戸石の城を真田が乗っ取る。」高白斎日記に知るされている。この「加沢記」の記述は、村上勢を戸石城に誘い込み多くの兵を討ち取ったという事です。と言う事は、戸石城を幸綱(幸隆)が手に入れた後という事になるので、天文二十年より後という事だ。それ以前の天文十五(1546)年三月の記録には「晴信公信州戸石に於いて村上義清と合戦御勝利。首百九十三人、栗原左衛門手に於いて首二十二討ち捕り晴信公に感状を賜わる。」と記されている。この時には武田晴信は、村上勢と戦い勝利を収めているようだ。
天文十九(1550)年には、
「八月二十四日、砥石の城(村上義清の属城)見積りに今井藤左ヱ門、安田式部少輔同心申す。辰刻に出て酉の刻に帰る。
八月二十五日、砥石の城見積りに又、大井上野助(信常)、横田備中守(高松)、原美濃守(虎胤)指し越さる。長窪の陣所の上、辰巳の方に黒雲の中に赤雲立つ。西の雲先なびく気にて。八月二十七日辰刻、長窪を御立ち。未刻、海野口(筑摩川西岸)向の原へ御着陣。鹿一陣の中をとおる。
八月二十八日、砥万の城際、屋降地(不詳)号に御陣すえられる。
八月二十九日午刻、屋形様敵城の際へ御見物なされ、御出て矢入れ始まる。酉刻、西の方に赤黄の雲、五尺ばかり立ちて紅ひの如くにして消える。
九月大朔日申刻、清野(村上一族)出仕。
九月三日、砥万の城ぎわへ御陣寄せられる。
九月九日、酉刻より砥石の城を攻める。敵味方の陣所へ霧ふりかかる。未の刻晴れる。
九月十九日、?須田新左衛門誓句。
九月二十三日寅刻、清野方より注進。高梨(政頼)・坂木(坂木城の村上義清)和談半途に於いて対面、咋日寺尾の城へ取かけらるるの間、真田(弾正宰隆)方は助けとして越られ候。勝沼衆虎口を一騎合同心始終存じ候。
九月二十八日、雨宮(現更植市・村上の幕下)と坂木は退出仕るの由注進。子刻(二十九日)真田弾正帰陣。
九月晦日、御馬納めらる可く之御談合。
十月一日、卯刻、御馬入れらる。御跡衆(殿軍)終日戦う。酉刻敵敗北。其夜望月の古地御陣所。終夜雨。
十月二日、峠(大門峠)を越えて諏訪へ御馬納めらる。酉刻、湯川(現茅野市)へ御陣所。
十月三日、上原に於いて万事を聞し召し合わせられ、方友へ御状つかわさる。
十月六日、上原を御立。
十月七日、府中へ御馬納められる。」
天文十九年八月二十四日~十月七日に記されていることが、俗に言う「戸石崩れ」と呼ばれる出来事のことか。十月一日に撤退し、殿軍に多大な損害が出た。「高白斎日記」には具体的な戦死者の名前は記されていないが、「勝山記(妙法寺記)」ではこの戦いに於いて横田高松が戦死したとある。戸石城の村上方の城兵は五百名、その内半数は天文十六(1547)年に晴信により攻められた志賀城の残党であったという。ここの城将は、「甲陽軍監」では、小県の国衆である楽巌寺雅方と布下仁兵衛の二名が見える。「村上家伝」には幸綱の弟、矢沢綱頼も村上方として戸石城に籠もっていたという。真田幸綱が、戸石城を手に入れるのはその翌年の、天文二十年である。志賀城の残党が砥石城の半数で士気は高かったというので、翌天文二十(1551)年の時は小県の国衆楽巌寺雅方、布下仁兵衛と矢沢綱頼を調略したものでしょう。この「加沢記」の記述は、この天文二十(1551)年~「四月九日、葛尾(村上の本城)自落の由申の刻注進。屋代、塩崎出仕。」とある天文二十二(1553)年の間のことと言うことになる。ただし、「高白斎日記」「勝山記」共にこの「加沢記」に記述されているものの関連する項目は出てこない。「加沢記」は、真田家のために書かれた物であるので、この記述を鵜呑みには出来ないが幸綱が戸石城にあって、村上義清追い落としの一翼を担っていたのはまちがいの無いことだろう。春原兄弟の内兄の小草野若狭守は海野の寄騎、弟の春原惣左衛門は幸綱の寄騎となったと言うことか。ただし、生島足島神社に奉納されている起請文の中には両名の名は無い。そこで考えられるのは、武田の直臣ではなく小草野若狭守海野信親(武田竜芳)の幕下、春原惣左衛門は真田幸綱の幕下と言うことかも知れません。
真田弾正忠幸隆公并祢津美濃守信直法体の事
天文二十年辛亥二月十二日、甲府において武田信濃守源晴信公御法体、法性院大僧正磯山信玄と御改名されたことにより、幸隆公もその節御相伴のため法体となって一徳斎良心と御名を改め入道となられた。嫡子源五郎信綱は信玄公近臣になっていたが、源太左衛門尉と名乗りを変えた。御舎弟矢澤右馬介は薩摩守と官途を賜り、勝頼公より諱の字を賜り頼綱と名乗った。祢津美濃守は村上合戦の時幸隆公と一緒に上州へ落ち延びたが、甲府へも一所召し出されたが、法体となり松鷂軒入道と名乗った。甲州没落の後徳川殿に召し出されて甲州、駿州に三百五十貫の領地を拝領したという。
<解説>
武田晴信公が天文二十年甲府で出家とあるが、実際は永禄二年(1559)の事で甲府の長善寺住職を導師として、「徳栄軒信玄」と名乗ったようである。「加沢記」では、「法性院大僧正磯山信玄」と記してあるが、名前も年代も違っている。弟矢澤右馬介頼綱の頼は勝頼の頼を偏諱されたものだと書かれている。始めの名前が、綱頼と名乗っていたことから初名海野棟綱の偏諱、武田家が勝頼に移ったことにより、勝頼の頼を偏諱として賜って綱と頼を逆さまにして頼綱としたものでしょう。
「高白斎記」に拠れば祢津元直は、天文十一年(1543)に 武田に臣従したとある。同年十二月十五日には元直の娘、祢津御寮人(祢津元直二男、正直の妹)が信玄の側室となる。信玄と祢津御寮人との間には、武田信清(米沢上杉藩家臣として存続)が生まれている。元直嫡男勝直は早世。二男正直(松鷂軒常安)が祢津の家督を継ぐ。この正直の正室は、武田信虎の娘である。三男信忠は真田幸綱の妹と婚姻を結んだが病弱のため、潜龍斎と号して真田昌幸に召し出され岩櫃城下、巌下山潜龍院(修験寺)を開く。以後、修験寺として江戸時代を通じて存続している。祢津勝直の嫡男月直は天正三年(1575)五月二十一日、長篠の戦いに於いて戦死している。松鷂軒常安は、真田家と共に武田家のもと上州攻略に力を発揮している。松鷂軒常安は天正十年(1582)には信濃国飯山城代に着いていたため難を逃れ、生き残っている。
武田家滅亡後の天正十一年((1583)松鷂軒常安は甥、祢津昌綱(潜龍斎の子)と行動を別にして、本家をこの昌綱(信光)につがせ自身は徳川家康に臣従した。この時姓を「禰津」から「根津」に改姓している。祢津昌綱(信光)は天正壬午の乱で、真田昌幸同様徳川、北条、上杉と主君を転々と変えた。同時期真田昌幸と祢津昌綱(信光)は北条方と徳川に分かれ、正行を小諸において二度にわたり昌幸軍を撃退している。この功により、北条氏政より本領安堵と甲斐手塚一千貫文、同清野で二千七百貫文の領地を与えられた。さらに、海野領より四千貫文の加増を約束されている。しかし、天正壬午の乱の収束を以て北条、徳川の和睦がなり、甲斐の領地を失う。それを持って北条から徳川へ、この時寝返った。真田昌幸が徳川に付くと、祢津昌綱は昌幸を嫌い上杉景勝に従う。最終的には、景勝の説得により天正11年(1583)九月五日真田昌幸に同心して三千五百石の家老として仕える。また支藩の沼田藩でも、千五百石の家老を務めた。吾妻では、祢津志摩守幸直と伝わる。江戸中後期の松代藩家老河原綱德が記した「本藩名士小伝」には幸直は元直二男と書かれている。しかし元直二男は、宮内大輔政直で祢津常安のことである。これは記述が合わないので、昌綱(信光)というのが信憑性が高い。「上田戦記」の上田城本丸で昌幸と将棋を指していた祢津長右衛門信秀は昌綱(信光)の子息で真田家次席家老小山田茂誠の娘を娶っていた。この家系は、松代真田藩の家老や目付を代々していた。
一方祢津常安の上州豊岡では、もう一人の甥である根津信政が継ぎ1602年には五千石加増され一万石の大名として「上州豊岡藩」となっている。その後信政嫡男政次が後を継ぐが、子がなく二男吉直があとを継ぐが、1626年吉直も若く死去して、無嗣断絶となる。以後連なる一族は幕臣となり、「鷹匠元締」となった。
ここで調べて分かったことは、祢津家本家、真田家家老祢津家共に「祢津潜龍斎(信忠)」祢津の嫡流元直の三男系が残ったという事みたいです。
岩櫃城由来之事并吾妻太郎附吾妻三家之事
上野国吾妻郡太田の庄平川戸鄕岩櫃城は近国無双の山城である。郡保のの内に山城がある。西側より東に向かい、南側は吾妻川である。その岸は岩石が峨々とそびえ立ち、高さ五丈、十丈に及ぶ。北方より南に向かい四万、沢渡の山中より流れ出るを山田川と言って、岸高く岩石が聳えている。両川の内、二箇所橋が架かり吾妻川の橋を太田の橋(田辺橋)と言い、大手の橋は山田川の橋という。そのほかは渡る場所無く、鳥でなくては通る場所なし。さて、両川の間に沢渡、山田、平川戸、郷原、矢倉、岩下、松尾という郷村があって、民屋八百軒を超えるくらいある。山城の高さ三十丈有り。岩窟そばだって所々松が生い茂り、入り口は東方より一口である。木戸口に大きな岩そばだちて、三の木戸梯子を掛けて登っていた。用水、木、沢あって谷は深くて、所々立て籠もる要害が多くあり、百万騎籠もっても狭くは感じない。城中町屋の北に岩鼓の要害があり。城地より他所に出る口、三箇所ある。追手白井口、市城には岩井堂の要害がある。渋川、箕輪へ出る口は柏原の要害、大戸口には手子丸の城、沼田口には八幡の要害、大塚壁谷の要害、尻高中山の城、その北方には武山、折田、仙蔵、山田、桑田、高野平の要害、榛名山への口山田沢、川戸郷その他数カ所の要害があって、究極の勇士を以て籠め置いて勤番させた。
そもそもこの城は永享年中尊氏公五代の孫、鎌倉公方持氏公若君ご誕生ある時御世継ぎ八幡二郎殿、御二男八幡三郎と申したが、悪しき行いを行い執事上杉民部太夫憲忠を誅伐を行ったため、白井城主長尾左衛門入道昌賢忠節を以て民部太夫の嫡子、顕定を守り立てようとこの城を築城して顕定を入城せしめ、持氏(成氏の間違いか?)公関八州の軍兵十万騎を引率して諸方より押し寄せたが、究極の城郭(難攻不落)であるので数度の合戦に及んでも、関東公方軍は中々攻め落とせなかった。成氏公苛立って多数を持って食責(兵糧攻)にしようと五万騎を加え、都合十五万騎の人数を持って山々里々尺地も残さず稲麻竹葦の如く取り囲んだが、かの山城を守っていた。昌賢文武の達人なれば、思案を以て四万の山、木の根宿峠越えで越州より牛数千匹寄せ、両の角にたいまつを結びつけて、嵐激しい闇の夜に諸方に追い出せば、この牛ども角に火が付いて動転して寄せ手の陣中に飛び入り、十文字に駆け入った。そのとき城中より昌賢下知して嫡子金吾昌信、三男彦四郎昌明差添へ八千余騎を二手に分け押太鼓を打たせ、わめき叫んで押し寄せれば、鎌倉勢猛勢と言えどもこの威に押され馬、物具、太刀、長刀、兵糧に至まで、皆小屋小屋に捨て置いて徒歩や裸足の有り様で、命助かりたい一心で一戦もしないうちに十五万騎の軍勢一夜にして崩れ去った。成氏公残党を集め、瞬く間に鎌倉に帰陣した。この威を持って長尾当国を討ち平らげ、元の通り上杉の御家督安泰にして、自身も白井に留まって一族そろって安堵した。この時哀れにも、長田の庄逢山(青山)の鄕遠通寺陣取られた大森式部太輔は、生まれ年十五歳にて大手の攻め口を請けていたが、長尾の家の子吉里金右衛門尉と中則橋にてしばらくあい戦い、夜中になってしまった。涙川(名久田川?)を渡ろうと吾妻川の落合へ馬を乗り入れ、水に溺れて死んでしまった。遠通寺の住持この事を聞き川を下り探しにいったが、これも水に入って行方知れずとなってしまった。この住僧、大森式部太輔と知り合いでもなかったにもかかわらず、一命をなくしたのはなぜであろうか。心得違いと言うことか。今、土俗の言葉に、物事の道理を違えることを遠通寺というのは、この事より始まっている。そもそもこの寺の由来を尋ねれば、法然上人九代の弟子行学上人この地に来て一仏刹を開基し、浄土宗仏法流布の道場数年の星雲を経てへて存続するも、この兵乱の折に住僧溺死しこの寺院、長く荒れ寺と成ったのは愚かなことである。
吾妻太郎殿と申すは、大織冠鎌足内大臣正二位が初めて藤原を賜った。淡海公不比等より三代乙麿公七代の孫、二階堂遠江守為憲東国へ下向して武蔵国を領した。その遠江守為憲より五世の維光二男維元が初めて吾妻郡を賜って太田の庄に居住して、吾妻太郎を名乗ったのである。これより子孫代々吾妻郡太田、長田、伊参の鄕を守護して繁栄したのだが、維光より四代の孫四郎助光の時、承久三癸未年(辛巳年の誤り)六月の乱に北条義時の催促に随って宇治川の合戦に溺死してしまってより吾妻家の家運、しきりに衰えた。
後、主君を太田の城(内出城)に閉じ込めて有るか無きのようにして、家臣大野越前、塩谷日向、秋閒三郎三人で領地を三つに配分して、秋閒三郎は太田の城二の曲輪に居住し、大野越前は平川戸稲荷城に居住し、塩谷は中の庄(中之条)和利宮の城に住んで、まるで三家の領地の如くであった。永享の兵乱の時は、まるで地頭ようであった。そんな所に文明の頃、由良信濃守源国繁隆起して兵乱の時、三家不和になって秋閒備前は大野に討たれ、大野は太田を領地とした。塩谷掃部介藤原治秀は門葉は広いので、大野度々理を失った。塩谷掃部介藤原治秀に一人の息女があり、甥の源二郎元清に嫁して仙蔵の城に居住したが、文明五年の春頃、夫婦確執があって離別したのだが治秀立腹して追い出した。息女行く当てがなくなり、大野の家に駆け込んだ。大野は戦の半ばで天の与える所と家の子斉藤孫三郎、富澤勘十郎を呼んで相談し、姫は蜂須賀伊賀に預けられ本城に屋敷を設営し、塞に住まわせ賓客(まろうど)殿と呼んだ。この姫、懐妊していたので塩谷方へ知らせる為、居城の大手に産屋を建て、大釜をすえ誕生を待ちわびた。ついに生まれいづる時となり、男子が誕生した。一門家の子大いに喜んで、その名を一場二郎と名付けた。さても塩谷は息女を取られ、源二郎子息も人質に取られて力なく降参して大野の幕下に降ったのである。これより大野下野守義衡嫡子越前太郎憲直、一郡の地頭と成って一場二郎を二男と称し、家臣斉藤三郎憲実、富澤勘十郎基康を相添としたのである。なほも塩谷掃部介を誅せんと、塩谷が一族蟻川、池田、尻高家臣割田、佐藤、中沢らに内通させ、塩谷掃部を誅伐し、一郡を討ち平らげ源国繁公に出仕して家は繁栄した。
さるほどに大野殿繁栄して岩櫃の城に居て、斉藤、蜂須賀を家老とした。太田の郷に先主の吾妻太郎殿一門の植栗河内守元吉という人が、大野に随っていた。大野はいささかの子細あって元吉退治すると思い立ち斉藤越前憲次を討手として命じた。斉藤も大野に恨みある所なので、岩下城の立ち帰り家臣富沢但馬基幸に相談して植栗へ討手と称して植栗が屋敷に攻め寄せた。もとより植栗は斉藤と近い親類なれば、元吉と一所に与して大野の舘へ押し寄せれば思いも寄らないことだったので、大野は腹十文字に掻き切り城郭に火を掛け、門葉一度に炎の中に飛び込んで滅亡した。憲次は岩下へ引きこもり鎌原、湯本、西窪、横谷、羽尾、浦野、蟻川、塩谷、中山、尻高、荒牧、大戸、池田以下の人々へ使いを以て事の子細を述べられ、今度子細を以て主君大野殿を討ち取った。各々わが幕下に属して戴きたいと申し上げたら、もとより知謀の斉藤であるので人々出仕して大将として認めた。上杉に出仕して、その後繁栄した。
こうしている所に、富澤多数の男子を持っていた。老後また一人の男子をもうけた所、斉藤大いに喜んで富沢但馬を呼んで、「其の方が老衰男子をもうけたこと、斉藤家にとって家長く相続できる瑞相である。去れば名を改めて付けるべし」と狂言にもてなした。おっしゃるには、「老後の子成れば重ねてまた生まれることなし、去れば富澤の子を止めたと言うことでその末は涸沢と成る。苗字を唐沢と改めるべし」とて即ち唐沢杢之助と名ずけた。さてまた成長して文武知謀の勇士となる。後、沢渡の鄕を知行してかの所に居住した。それより富澤、唐沢両家に分かれて斉藤の老臣となる。
頃は大永の時代となる。憲次の嫡子越前太郎憲広法体して一岩斎入道と言った。次息女は、大戸但馬守真楽斎入道の妻となり、御子四人おった。長男太郎憲宗、二男四郎憲春、女子は三島の地頭浦野下野守妻である。後に羽尾治部入道の妻となる。末子城虎丸、これは武山の城差し置かれる。岩櫃の城山に人別松を植えさせ、松一本に一銭宛て行われた。銭を持って松の数を分かるようにした。およそ十万本より多くなったよう。
<解説>
ここでは、まず吾妻太郎助光と由緒が述べられている。この項では、藤原二階堂流としている。そのほか、藤原秀郷流で、下河辺行平と同じ系統と、村上源氏流吾妻氏とある。吾妻の古文書では、憲行、行禅、行弘、行基、行連、基国と続き、基国の時真田の滅ぼされている。「加沢記」では、斉藤系図をもとにしているように想う。「実際にはどれが正しいか」、と聞かれれば「分からない」というのが正直な所である。この吾妻三家の記述は、どれをもとにしているのかは分からない。そして、どれも根拠を求めることは出来ない。吾妻氏については、「吾妻鏡」の中に複数回吾妻氏の記述が見られるので、存在していたことは確かなのだが。ただ、吾妻太郎行盛の墓だけは存在している。しかし、斉藤氏の墓は、何処にあるのか全く分からないのが現状である。大野氏が滅ぼしたとされる秋閒氏、塩谷氏もその後でも存在していることからこれも疑問が残る所ではある。そして、岩櫃城の記述があるが、恐らくはこの頃岩櫃城が存在していたのか記録がない。また、築城伝説で長尾昌賢が築城したというのは信憑性に欠けると思います。富澤と唐沢の記述も、物語としては面白いと思うが、その根拠はない。ただ、富澤も唐沢もこの吾妻にはたくさん名乗っている人達が現在でもいるのは、事実です。
沼田城築くこと附家伝
桓武天皇の皇子一品葛原親王に二人の御子がいた。兄を高棟王を称し、弟を高見王と名ずける。子孫は今の西洞院流である。高見王の子息上総介高望王に初めて平姓を賜り、子孫を平氏として武家になる。嫡孫清盛は悪行を行ったので寿永元暦の間に頼朝卿興りて門葉ことごとく滅び、平氏断絶する。高望王の末為道、三浦長門守と号す。為道八代の末、三浦景泰上州利根の庄を領して、利根薄根の両川を前に当て沼田の庄に城郭を構え、住んでいた。されば、沼田景泰と名乗っていた。沼田氏の元祖である。(以下欠文)
鎌倉北条九代の時文諸国より大番役を務めたと伝え聞く。その人々には、沼田上野介、発地薩摩守、久屋三河守、下沼田豊前守、岡谷(おかのや)平内、石墨孫三郎、小川河内守、川田四郎幸清入道である。後醍醐天皇の時勢と伝え聞く。大番役を務める賞として禁裏より拝領したという。沼田殿へは鞍鐙作りの御免許、代々作の名人故に居城を鞍内(倉内)と言った。
発知殿へは竜田紅葉一本在所は持参植え置き、天神の社を建てられた。よってそのところを竜田と言った。岡谷殿は岡谷村守護不入の御綸旨を拝領した。下沼田殿は子息に真言宗の僧がいた事により高野山北の防、清浄心院を下沼田氏に末代まで住持職の綸旨を拝領した。今に至るまで下沼田氏にてこれを継ぎ来ると伝わる。
小川殿には馬ヤキガネ一本拝領する(牛馬の尻に焼き印を付ける金属)。いかなる病馬もこのヤキガネを当てれば本復奇妙の器物である。
久屋殿は鉈一丁、これは何の木を切らんと思うにその鉈を当てればそのまま倒れるという器物である。
石墨殿は、一年に二度咲く牡丹を拝領した。
川田殿は一人の子息(息女)を持っていた。その名を円珠申し、歌人なり。この歌を叡覧の願い相叶い一首の歌を(禁裏へ奉る)
竜田山もみぢを分けて入る月は錦に包む鏡なり
この歌、叡覧あって
かみつけや沼田の中に円かなる玉のありとは知らまし
と御製を下し遊ばさることとなり。
その頃天下不穏諸国国司下向なり。上野国那波郡へ後醍醐天皇第六の皇子成良親王征夷大将軍に任じて、御下向なり。その時沼田の守護には大友刑部大輔殿お下りあって川場の鄕におわします。今に屋敷跡あり。大友主観音をご信仰なされ、利根郡に三十三観音を建立、舘より十五町程言った所に一宇の御堂を建て、舘より廊下を掛け参拝したという。ここを別所名付けたという。また、鎌倉より慧済禅師を招請し、始めて青竜山吉祥寺開基されたという。御奥方も信心深くあらせられ、大友主逝去の後清竜山境内に大智庵祐宗比丘尼と名乗り、お住まいになった。その頃如意庵に観世音を建て、像の内へ仏舎利を籠められました。その像内に書き付けが有り。その文に曰く。
(群馬県史による)
大日本国上州利根之庄川波鄕青竜山吉祥寺境内之大智庵祐宗比丘尼大友刑部太輔之御内 成。仏舎利於安金塔二六時中勤渠拝尤間断有事勘原吾弗幾、後世真不具之者為容易如件 思惟而安修観世音摩訶薩埵之像霊験衆生如影随形一切所求速編成就衆生信進共 成仏応 安三年上章閹茂侠鐘十五日吉祥現
住沙門大拙祖能襲記
「大日本国上州利根の庄川波の郷青竜吉祥寺境内の大智庵祐宗比丘尼は、大友刑部太輔の御内なり。仏舎利を金塔に安んじ二六時中勤しみこりたきをがみすること間断無し。時有りて思えみれば吾が命幾ばくもあらず、後世真不具の者に(参拝を)容易ならしむが為、件の如く思惟して観世音摩訶薩像を安修す。霊験猶影の形に随うが如く一切所求速やかに成就し衆生の信を進め、共に成仏せんことを。
応安三年上章えんぼう夾鐘十五日
吉祥現住沙門大拙祖能つつしんで記す。」
吉祥現住沙門大拙祖
(群馬県史のよる)
大日本国上州上野州利根荘青竜山吉祥禅寺如意庵、水晶澐如来舎利安之、観世音菩薩薩 訶埵像、其数一百五十粒。伏願此観世音霊感如生凡有所祷、如鏡現形如谷答響、一々其 所求悉皆円満
応安五年歳次辛壬子(みづのえね)八月廿二日
吉祥沙門祖能謹誌(以下欠文)
「大日本国上野の州利根の庄吉祥禅寺如意庵、水晶両雲の如来舎利はこれを観世音菩薩薩 訶埵像に安んじてその数百五十粒、伏して願わくばこの観世音の霊感生けるが如く、すべて祈る所があれば、鏡の形を現すようである、音の響きに答えるように、一々その所求悉皆円満になりますように。
応安五年歳次八月廿二(にじゅうに)日
吉祥沙門祖能つつしんで記す。
景泰□代孫上野介景康代に至り、長禄二戊寅(つちのえとら)年、利根・薄根両川の落合の岸、当郡惣鎮守武尊神宮社場当国無双の地たるに依って社人□□□宮□髙井但馬を招き、城を築かん事を請い願う。さて明神の社は根岸にご建立あって城郭に築かれた。この石をさして汚れているので殺生石と世の人は申していた。
「この石以下文章不明」
<解説>
青竜山吉祥寺如意庵の観世音菩薩像の中に入っていた文書をもとに、沼田大友氏の由来を述べている。しかし、この南北朝期に大友刑部大輔氏時は九州での活躍が期されている文書が残されている。氏時が飛び地として上州沼田の庄を領していたかもしれないが、氏時自身が沼田に居たと言う根拠は未だ見つかっていない。氏時は足利尊氏の寵愛を受け、猶子となっていたことから飛び地としての領有は否定できないと思われるが、氏時自身が沼田に居たと言うのは考えずらいと思う。しかし、氏時の一族がこの地に赴任していたと言うことは考えられるでしょう。まあ、この観世音像の中から出てきた、二通の文書と地元の伝承を交えて加沢平次左衛門が書き記したと考えるのが妥当だと思います。
沼田了雲斎入道御繁昌之事
永享十一(1439)年鎌倉の公方威を失いなされてより以来、都鄙静かではなく、就中関東大いに乱れて在々所々に片時も合戦がやむことが無かった。上野介長忠の代である。法名は怒林院殿と号した。文武に勝れた人である。武略を巡らし沼田近辺の城主を幕下に付けられ嫡子勘解由左衛門尉顕泰の代に至って利根・勢多・吾妻郡の内須川の鄕を限り、中山・尻高・平方・米野・祢利・黒川・深沢・五乱田あたりまで領していた。その内の城主皆幕下に属し、当国の管領上杉民部大輔顕定に従い平井の城は出仕していた。顕定公より御諱の一字を賜り顕泰と号す。御奥は長野信濃守殿の御女である。御子は多くおられたという。嫡子上野介殿は光源院義輝公の近臣に属し、近江の国にて御地を賜り在京していた。二男三郎殿嫡子に立てられ、平井に出仕されて上杉憲政公より一字を賜り憲泰と名乗っていた。十八才の御時上杉の老臣群馬郡白井城主長尾金吾昌賢三代の孫長尾左衛門景春の御婿となるが、程なく御逝去されたよし。三郎殿七歳の御時、母公と老神へ湯治した時湯小屋の上の巌に墨絵で馬をえがきけるが、そのご農民有徳の僧を持って繋ぎ馬に書き換えれば後は放たれざるとなる。後入湯の時御母公が詠んだ歌がある。
谷深み絶えぬ松風波の音ただ寂しきは老いが見(老神)ぞかし
三男六郎殿は野州佐野宗綱のご一族赤見殿と申すは顕泰の御妹婿であることで、女人一人おりますにより御婿名跡に六郎殿を立て申した。そのとき赤見殿より六郎殿御迎えのため家臣兵藤駿河守と申す侍を沼田に差し越させた。四男弥七郎朝泰沼田倉内城主で、厩橋城主北条弥五郞殿御婿になられました。御妹御一人おりましたが、長野信濃守殿御仲立ちにて群馬郡(碓氷郡)安中の城主安中越前殿へ御祝言となる。これを安中御前と申した。顕泰は入道して万鬼斎と号し弥七郎殿へ倉内城をお譲りになられたが、御末子平八郎殿へ領地の三分の一を分け与え、御父子一所に下川場鄕に御屋敷を構えて隠居しました。弥七郎殿御童名米童殿と申したという。三歳の御時吾妻郡須川鄕箱崎城に住まったという。そのとき池ノ原という所に諏訪大明神を建立され、別当に茶坊主広伝と申す者を山伏とされたという。御陣之御供にもでたという。子孫光学院と名乗り、今も別当である。
<解説>
沼田氏の由緒を記した一文である。沼田氏は三浦の一族で、山之内上杉氏の家宰長尾氏と同族である。上野介長忠の代に、上杉顕定にしたがっていたとある。上杉顕定が、藤岡の平井城が本拠であると記しているが、これは間違いである。顕定はの本拠は、最初五十子の砦で、長尾景春の乱の後は武州鉢形城が本拠であった。顕定が越後で長尾為景(上杉謙信の父)に敗れ戦死すると、顕実が関東管領を継ぐが上杉憲房が平井を本拠として顕実に対抗する。顕実は鉢形城で、憲房が平井城である。ここでは、平井が本拠であると記しているが憲房、憲寛、憲政と三代がここを本拠とした。ちなみに、子持の白井城は越後上杉家の本拠で享徳の乱、長享の乱於いて、越後上杉の軍が常駐していた所です。現在の説では白井長尾家の成立は長尾景春の子、景英が白井長尾家の初代という説が主流となっています。ここでは触れていないが、沼田万鬼斎と末子平八郎景義と弥七郎朝泰との騒動を池波正太郎氏が「まぼろしの城」という小説で描いている。興味ある方は、一読してもらいたい。
鎌原の忠節を以って信玄吾妻郡御手に入る事
信玄公は天文年中より信州へ出張有りて十六歳の御時平賀玄心法師を討ち取り平賀の城を攻め取り給(たま)ひ、それにより上州へ御手立て有り。就中永禄の始めより折々出張有りけり。爰(ここ)に清和天皇より二十八代の胤孫(こうそん)鎌原宮内少輔と云ふ者有り。信州上州両国の境浅間岳の麓、三原の庄を数代領せし地頭なりけるが、文明の頃より管領上杉民部太輔顕定に属し、関東に伺公(しこう)しけるが天文年中より憲政威を失ひ給ひてより所々城主そはだち兵乱しければ、大身は小身を掠めける折なりければ其の頃吾妻の大田の庄、岩櫃の城主斎藤越前守藤原憲広入道一岩斎近辺を横領しければ彼が下知にぞ随いける。鎌原熱々(つらつら)世上の成り行きを見るに、信玄公日を追ひ威を揮ひ給ひける、何卒(なにとぞ)幕下に属せんと明暮(あけくれ)時を待ちて年月をぞ送りける。幸ひ一家の幸隆(幸綱)本領に帰り小県郡に住み給ひければ、幸隆(幸綱)を頼まんとて嫡子筑前守と相談あって、この由を申されければ、幸隆(幸綱)も斜めならず喜び、小諸の城主甘利左衛門尉こそ信玄公無二の臣なりければ、左衛門尉を以って披露し給はんとて信玄公の信州出馬を待ち奉りけるに、頃は永禄三年の春信州平原に於いて筑前父子御礼し給ひければ、信玄公喜悦浅からずして、何卒計策を廻らし、斎藤を討取り給へかしと言ひてければ旦暮(あけくれ)その謀を廻らしけり。翌年11月西上州へ出張の節鎌原へ御書有り。
調略故其許(そこもと)時宣(しぎ)然るべき様に候か。本望に候。就中(なかんずく )高田降参、今日は馬を休め。明日より国峰に向かひて行(てだて)に及ぶべく候。近 日人数を分ちその節へ遣はすべく候条、弥(いよいよ)相調(あひこしら)へ候様油断 なく計策専一に候。
恐々謹言
11月十九日
鎌原この御書を謹んで拝見して後、尚以て斎藤方へ不忠にに見えければ憲広入道も覚え束(つつがなく)なく思はければ、同じ三原の庄の内羽尾道雲入道は鎌原と一族なりけれども近年不和の儀有り、羽尾を以て鎌原を討つべしと評定し給ひて、塩野谷将監入道・羽尾入道両手して鎌原が館へ押し出し合戦有りけるが、究竟(くっきょう)の要害なり、一族浦野下野守・湯本善大夫・横谷左近等が味方をして横切りしきれば、斎藤も叶はずずして憲広は大戸真楽斎を以って和談しけり。されども斎藤も鎌原に心を許す事成ければ(無かりければ)鎌原も敬信して見えたり。何卒この度の序を以て謀(はかりごと)を廻らさんと思ひ、斎藤が家の子岩下の地頭富沢が惣領富沢但馬守行連と云ふ者有り。これは横谷左近太夫が姉婿なり。彼を以て入道の甥斎藤弥三郎に知音して入道に二心なき様にもてなし、岩櫃を攻め取るべしと思ひ、弥三郎に申し入れければ、案に違はず入道も心打ち解けたりければ、この儀は早々甲府へ注進せんとて黒岩伊賀を以って密かに甲府へ注進しければ信玄公感じ給ひ御返礼有り。
翰(かん)礼見其の谷の模様申し越され候。何れも承り届け、余儀なく候。殊(こと) に密々の儀其の意を得候。然れば早々着府待入り候。委曲は甘利所より申し越すべく候 。恐々謹言
六月廿七日信玄判
<群馬県史資料編より>
とぞ書かれたりけり。黒岩氏此の返礼を取り持ちて忍びやかに在所に立ち帰りければ、宮内少輔悦びて黒岩が在所今井の郷に池川殺生一切免許し給ひてけり。長男筑前守を甲府へ参陣しければ信玄公斜めならず種々褒美賜って斎藤が事一々御尋ね有り、さらば討手を差向くべしとて幸隆(行綱)公甘利左衛門尉を大将にて旗本倹史として曽根七郎兵衛其のほか信州先方芦田下総守・室賀兵部大夫・相木市兵衛尉・矢沢右馬介・祢津宮内太輔・浦野左馬尉、都合三千余騎、同年八月(日付追って考ふべし)。大戸口、三原口両手に分かれて押し寄せ給ひければ、斎藤叶ひがたくや思ひけん、善道寺の住僧を以て降参を請ひ給ひければ、人質を受け取り、一戦に及ばず帰陣有りけり。
<解説>
鎌原氏と羽尾氏の確執は、吾妻に残る伝承にも出てくる。鎌原氏と羽尾しは同族であるが、領地を接していることから以前からこの境界をめぐってもめていたのだと思う。「吾妻鏡」には、羽尾の領主海野幸氏との記述があるので、元々は鎌倉時代の初めは三原の庄は一つの庄で海野氏の領地であったのでしょう。それが鎌倉時代の中、末期ごろに鎌原と羽尾に分かれたのかもしれません。海野氏は、鎌倉時代から四阿山(あづまやさん)信仰で西吾妻に開発領主として入ってきたといわれている。鎌倉時代海野の一族、下谷将監という人が三原の庄に入ったとの伝承もある。この下谷将監の末裔が、鎌原氏と羽尾氏であるということも考えれるが、確証はない。ここには、大戸真楽斎の記述もあるが大戸氏の本姓は、浦野氏である。信州街道沿いに滋野一族の各氏が、開発領主として鎌倉時代の初期のころから入っていたのだと思います。さてここで、横谷左近や浦野下野守などが登場するが羽尾氏が最初鎌原氏を攻めたとき、この両氏は鎌原についている。そしてこの後、岩櫃城に真田幸綱(幸隆)を大将として攻め寄せた時、横谷氏と浦野氏は斎藤方についている。この「加沢記」によると岩櫃城は三回攻められているが、その二回はこの横谷氏、浦野氏ともに斎藤方に与していたように記述がある。これを見ると小さな地方の小豪族は、自分の家を守るためその去就に苦慮しているのがうかがえる。ただし、この岩櫃城であるが近年の研究では岩櫃城は武田が築いた城であり、その西方三キロメートルのところにある岩下城が斉藤氏の本拠であるというのが定説となっている。
鎌原と羽尾合戦の事
爰(ここ)に海野の松葉に羽尾治部少輔景幸と云う者の嫡子、羽尾治部入道道雲の二男海野長門守幸光、同海野能登守輝幸とて無双の勇士、殊(こと)に三男能登守、力万人に勝れ兵法修行にて師たる士なりければ、斎藤入道別して懇切有て情け深かりければ、兄弟も無二兄弟も無二の臣にぞ属せられる。ある時羽尾入道岩櫃へ出仕し給ひければ、斎藤越前守宣ひけるは「さる秋信玄より討手を差向けられけるが、世習に順ひ降参とは申しつるが、偏(ひとへ)に鎌原が表裏故なれば憤(いきどほ)り止むこと無し。羽尾入道の行(てだて)にて鎌原を討つに若(し)くはあらじと申されければ内々某(それがし)も心がけたる所なりとて、永禄三(1560)年十月上旬羽尾入道道雲、海野長門守幸光、富沢加賀守庸運(つねゆき)、湯本善大夫、浦野下野守、同中務太夫、横谷左近将監六百余騎、鎌原が要害にぞ押し寄せたり。鎌原も予て用意の事なりければ、嫡子筑前守を赤羽根の台に出し、西窪佐渡守を大将にて家の子今井、樋口を鷹川の古城山へ差し登せてその身は要害にぞありける。かかる所に羽尾治部入道道雲、海野長門守一手に成って筑前守が控へたる赤羽根の供養塚の辺にぞ寄せたりける。互に火花を散らし戦ひける程に、仏坂西川の地辺にて追ひ戻し散々に戦ひけるが、難所なれば大戦はならざありけり。かかる所に大戸真楽斎加勢して舎弟但馬守に手勢二百余人相添へ、須賀尾峠(万騎峠)を越えて狩宿へ寄すると告けければ、鎌原も叶はず、さらば手段(てだて)を廻らし、まずこの度の軍(いくさ)を遁(のが)れんと思ひ、常林寺の住寺を使僧にて降人に出たりければ、左右(さう)なく和談したりけり。この由信玄公へ注進ありければ、斎藤と鎌原不和にして度々の兵乱もちろん小身の小競合(こぜりあひ)とはいひながら小事は大事の基なり。この根源をたづぬるに、羽尾入道領地を争ひ、鎌原と不和の故なりければ、倹史を以て御決めあらんに如(し)くは無しとて、頃は永禄五(1562)年壬戌(みずのえいぬ三月、甲府より三枝松(さいぐさ)善八郎、曾根七郎兵衛、信州先方室賀入道を以て境目御極めありければ、斎藤も羽尾も喜悦浅からずして倹史は帰府あられけり。かく御極めありける所に羽尾入道数代相伝(の)領地、古森、与喜屋の両村を鎌原方へ御付け在りし事、鬱々(そうそう)晴れがたしとて、この旨斎藤に申されければ、尤(もっと)もなり、さらば鎌原に申すべしとて山遠岡与五右衛門尉、一場左京進を以て申されたりければ、一旦信玄公より御倹史を以て赤川、熊川両川の落合を限り取り決めありける上にかく宣ふことは一家浮沈の安否なりとて、同年十月在所を払って信州佐久郡へ一門悉(ことごとく)退去す。この由甲府へ注進したりければ信玄公より翌年三月甘利利左衛門尉を以て鎌原が許へ御書を下され、信州にて領地をぞ宛行はれける。その文曰く、
其方進退の儀に就いて斎藤越前入道の所へ存分申し届けられ候と雖も承引無きの上、在 所を退き信州へ罷り越され候上は、羽尾領に於いて相渡し候知行の如く、卿か相違なく 海野の領の内を以て出し置くべく候。後遍も尚忠浅からざる義に候間、疎遠に思はざる の段、甘利口上あるべく候。恐々謹言。
永禄五年壬戌三月廿六日
信玄花押同前
とぞありけり。かくて鎌原が要害へは羽尾入道入れ替わって居たりけり。羽尾入道風流者にて常に茜染(あかねぞ)めの小袖を着して浅間山の麓モロシ野に遊猟し、或は鹿沢の湯などに入湯し、安楽にこそ暮らしけれ。鎌原は小県郡にて領地を賜り安堵したりけるが、羽尾が振舞を聞くにつけても故郷へ帰らんことを旦暮(あけくれ)思い暮らし、故郷の農民らに恩賞の者方へ内通したりければ、羽尾入道同年六月万座山へ浴湯したる由告げ来たりければ、幸ひなりとて幸隆公、祢津覚直、甘利利左衛門尉より少々加勢を乞ひ、本領へ来給へば羽尾は留守なり。嫡子源太郎も岩櫃へ参りければ、留守の者五六十人計り鎌原水の塔を越え、堀厩の辺甘利殿加勢は砂塚、はなだ坂の辺りへ来ると聞くより早く城を空けて逃げ去りけり。一戦にも及ばず元城へこそ入りちりけり。所々を見るに羽尾入道貯え置きたる米穀兵具その外沢山なりければ、羽尾衆我ら待ち設けの支度備はるとて、加勢の軍兵へ馳走して信州へこそ帰されけり。羽尾入道この由を聞き、ただ茫然として力無く、羽尾に帰らんと道を塞がれたり。またこのの儘にてあるならば敵寄せ込むは治定なり。信州へ落ちんとて、六月下旬万座山の湯を発って山越しに信州高井の郷にぞ落ちたりけり。この由斎藤入道聞き給ひて、甲州加勢なき前に鎌原を討ち取るべし、小勢にて叶ひがたし謙信公へ随身せんとて長尾左金吾入道(憲景)へ善道寺の住僧、同苗弥三郎、唐沢杢之助を以てこの由斯(かく)と宣ひければ、一井斎聞いて、願ふ所の幸ひなりとて即ち越後へ中山安芸守を以て披露すべしとありければ、中山よりは家臣平方丹波を以て申し述べたりけり。謙信公も御喜悦し給ひて斎藤方へも御書を遣はされければ、斎藤も早速出仕願ひ奉ると雖も兵乱の中なれば自身叶はずして甥の斎藤弥三郎、富沢但馬守を以て権田の造りの矢の根千、熊皮二枚差し上げ、御礼(臣従の誓約)相決まるなり。使も御褒美として白布二十反宛拝領したりけり。かくて羽尾入道は数月信州高井野に居たりけるが、何とぞして故郷(ふるさと)帰らんと計略(はかりごと)を廻らして、鎌原が老臣樋口と云ふ者あり、彼は羽尾にも親類なりければ、彼がもとへ内通し、鎌原を誅せんに於いては鎌原一跡を宛て行ふべし云ひやりけり。斎藤入道も海野長門守を以てこの旨を申されければ慾心に義理を忘れしものなるべし、樋口この儀同心して高井野へ申しけるは、「万座山に大雪積もらば叶ふべし。九月中旬に出馬し給へかし。さらんに於いては寺場に陣取り、先勢を門貝(かどがひ)を下りに向け給はばこれは西窪が防ぐべし、干俣通りに米無山へ打登り、大前へ出給(いでたま)ふべし。中城、外城両所には嫡子筑前守守り居て、中々寄すべき便無し。大前へ働き給はば宮内自身出(いで)向かうべし。その時我も供すべし。宮内は常に黒なる馬、我は葦毛(あしげ)の馬に乗りて出づるべし。黒なる馬を目掛けて鉄砲にて討ち給へ」と固く約束合図を極めければ、案の如く羽尾入道高井野より加勢ありてその勢五百余人、同年九月上旬万座山を越へて干俣、米無山に陣取って見えければ、宮内家臣樋口大将にてその勢二百余人鉄砲上手十人召し連れ、前後に是を囲ませ、大前表へ発向す。鎌原は黒なる馬に銀覆輪の鞍置かせ、黒糸威(くろいとおどし)の鎧着し、同じ毛の五枚(錣(しころ)の)兜の緒締め、三尺五寸の熊皮の尻鞘(しりざや)、二尺七寸の打刀、十文字槍横たへ、重藤の弓持ち出でけるが、鎌原が運の続ぐべき瑞相にや、用害を出でて鳥居川を渡る時乗ったる馬前膝折って伏しければ、この馬は足立ち悪しとて樋口がが乗ったる葦毛の馬に乗りかへたり。樋口もさすがにその時に至りては辞退せんこと力無く、乗り換へてぞ供したり。敵は大前の上原に控へて喚(をめ)きければ、樋口の予(かね)て合図の事なりければ、鉄砲の音しける度ごとに今ぞ最後と思ふにより、宛(さながら)ら進む気色なく、ここかしこにて猶予して控へければ、鎌原には一町ばかりは引き下りたり。羽尾この由見るよりも、樋口は内通の者なりければ後ろに控へて進まず。高井野山中にて下針を撃つ(程の鉄砲の名手)あり。彼を頼みて来りければ、合図の敵を一鉄砲にて撃ち取らんとの儀なれば、猟師物陰に狙ひ寄って撃ちかける程に、無残や樋口が胸板打ち抜いて、遥かに見えたる郎従一人、頭をすと撃ちぬかれ、犬居にどうと伏したり。羽尾この由見るよりも、大将は撃ちたり、郎党の樋口は味方になる、子細は無きぞ者どもとて、弓鉄砲も袋に収め、弁当を取り出させ、酒盛りせんと悦びける所に、鎌原は恙(つつが)無ければ一度にどっと押し寄せければ案に相違して見えける所に、草津の谷より湯本善大夫、浦野義見斎、鎌原に合力せんと石津の辺より寄せ来たりけり。善大夫が嫡子湯本三郎右衛門といふ者はその頃羽尾入道に属しけるが、日頃羽尾に恨み深ければ、心変りして鎌原と一所に成る。羽尾入道叶はずして只一騎川について漸々に平川戸にこそ落ち行きたりけり。高井野の加勢は這々(はふはふ)の態にて野暮れ山暮れ知らぬ山路を迷ひて出て、日数七日十日にて古里にぞ逃げ帰りけり。この由甲府へ注進せられければ、斎藤も謙信に属する由、小勢にては叶ひがたし、加勢を指し加へらるべし。兵粮は小県より給すべしとて、祢津、芦田、甘利衆番なり。鎌原、長野原二ヶ所の用害にぞ籠め置かれけり。兵糧は幸隆公より国の催合(もやひ)を取って続き賜はれけり。その時幸隆公へ御証文あり。その文に曰はく、
鎌原宮内少輔俵物一月二十五駄文相違なく勘盧すべき者なり。
仍て件の如し。
永禄六(1563)年癸亥(みずのとい)五月三日
信玄(竜の御判)
斯の如く御評定ありて、鎌原宮内、同筑前、西窪佐渡守、湯本善大夫、斎藤入道に挑み合ってぞ居りけり。この頃横谷は斎藤が味方なりけり。
<解説>
鎌原、羽尾の同族の争いからいよいよ吾妻郡も、武田VS上杉の戦いに巻き込まれていく。まず、武田の裁定で古森、与喜屋の羽尾旧来の領地が鎌原領となった。もちろん、羽尾は承服できる裁定ではなかったのでしょう。しかし、大勢力武田に対して異議を申し立てるのもはばかばれる。武田がこの地を離れてから、動いてくる。まず、羽尾は岩櫃の斎藤を頼り、斎藤は単独では武田に対抗できないので越後上杉とよしみを通じるようになる。上杉謙信の関東遠征の時に吾妻も攻められ。これに拠って上杉方になったとの説もある。しかし、ここでは加沢記の記述の解説であるので加沢記の時系列で意見を述べる。まず羽尾方が、攻めにはいるが、のときは浦野、横谷、大戸氏などが斎藤に付斉藤有利に事が運ぶ。しかし、武田氏が吾妻へ本格的に侵攻してくると皆、武田になびいてしまうのです。悲しいかな、片田舎の小豪族がいかに苦慮しながら生き残りをかけた戦いをしていたのがわかります。領地については、吾妻郡は江戸時代初めで約2万石と言われている。そうすると、この加沢記の兵力の記述は多く見積もっていることがうかがわれます。2万石で500人程度の動員力ですので、200人VS300人とか100人VS400人といった人数で戦をしていたのでしょう。こういう記録、軍記物などみな兵力を盛って表現していることが多いので、この点は注意が必要になると思います。
長野原合戦之事
永禄六(1563)年九月下旬の事なりけれ。長野原の要害には幸隆(幸綱)公舎弟常田新六郎大将にて、湯本善大夫、鞠子藤八郎、加勢は芦田下総守の手の者依田彦大夫、室賀兵部大輔手の者小泉左衛門勤番なりけるが、斎藤越前守は白井より加勢を請け、斎藤弥三郎、羽尾入道、海野能登守大将にて、植栗安房守(安芸守?)、荒巻浦野中務、斎藤宮内衛門、富沢豊前、蟻川源次郎、塩野谷将監入道、割田掃部助、富沢勘十郎、横谷左近、佐藤豊後、割田新兵衛、唐沢杢之助、同右馬介、加勢には白井八郎、神庭三河入道、牧弥二郎、相髄ふ侍には野村靱負、飯塚大学之介、村上牧之介、大島式部、石田勘兵衛都合その勢ハ百余騎。斎藤弥三郎、塩野谷将監は暮坂を経て白いの加勢二百余騎、都合三百余騎小雨川を打ち渡って湯窪の辺に押し寄せたり。追手は羽尾、浦野、植栗五百余騎大城山(王城山)へ駆け上って用害を見下ろし、合図の貝を吹き立て、鬨をどっと作り、鉄砲を撃ちかけける程に城中には民農業の時分なれりければ、在家に下りて小勢なりければ、須川、琴橋両所の橋を引いて防ぎければ王城山より材木を伐りこみ、須川を一時に埋め陸路にして喚いて懸かりければ、大将常田怺(こらえ)へ兼ね、自ら諏訪明神の前に出向ひて防ぎけるが、羽尾と相戦ってしまいに討たれ給いけり。究意の用害なりけけれども大将討たれ小勢なり。難所の事なりければ鎌原の勢加勢も及ばざりければ、夜中に用害を忍び出て鎌原の城へぞ集まりけり。羽尾喜悦して即ち用害に入れ替わってこそ本領を横領しけり。この由甲府へ注進したりけれどもその頃越中駿河へ御働きありければ御加勢も叶ひ難く、空しく月日を過ごし行きけり。
<解説>
これは、鎌原氏の吾妻復帰に伴い領地を失った羽尾氏が白井の加勢を以て斉藤氏の後援で、旧領回復を行ったものです。何百騎とある兵力は大部もってあると思われるが、実際は常田勢100人、斎藤勢300人程度の戦いであったと思います。この決戦の場所となる、長野原城跡は長野原町の北側山一帯に縄張りしてある城です。ただし、水はなく長くこもれるしろではなかったのでしょう。常田勢は、小勢でも有り本来であれば城に籠り後詰を待てばいいのでしょうが、籠城戦は御詰あっての戦いです。籠っていてもじり貧になるのは明らかですので、当然出る戦いになるのは必然だったのでしょう。これにより真田幸綱の、斎藤盗伐が本格化してきます。
斎藤入道没落并沼田加勢の事
永禄六(1563)年癸(みずのと)亥八月下旬の事なりけり。斎藤越前入道一門家の子を集め、評定しけるは、さる頃より羽尾治部入道と鎌原と不和の後は甲州へ鎌原忠節ありければ、大戸・浦野もその振り見えければ、沼田万鬼斎・同三郎憲泰と和睦して加勢を乞ひ、鎌原を退治せんと思ふは如何と申されければ一統同心して中山安芸守を以て沼田殿へ申されければ、憲泰公同心し給ひてけり。鎌原宮内少輔この由を聞いて真田一徳斎入道幸隆公を以て甲府へ注進せられければ、速やかに誅罰あらんとて真田へ下知ありて、甲府より倹史として幸隆公の三男武藤喜兵衛尉昌幸公・三枝松土佐守小県郡に着陣す。大将は一徳斎、相従ふ人々には矢沢右馬介・常田新六郎俊綱嫡子源左衛門尉信綱・祢津宮内太輔元直嫡子長右衛門尉利直・海野の家の子小草野孫左衛門・相木市兵衛尉・芦田右衛門佐・鎌原宮内少輔嫡子筑前守・湯本・西窪・横谷、都合三千余騎を二手に分け、横谷雁ヶ沢・大戸口へ押し寄せ、大戸口は祢津・芦田・矢沢を向けられけるが、大戸真楽斎、舎弟権田の地頭但馬守を以て人質を出し降参す。かかりける所に沼田三郎憲泰公この由を聞こし召し給ひて、舎弟沼田弥七郎朝泰を大将にて、山名信濃守・発知図書介・下沼田道虎入道・名胡桃の鈴木右近(鈴木主水?)、そのほか師大助・山名弥惣・西山市之丞・塩原源五左衛門・原沢惣兵衛・増田隼人・根岸左忠・小野・広田・深津・真下・小川の一族、都合五百余騎、永禄六(1563)年九月上旬沼田を発って岩櫃に着陣す。白井城主長尾左衛門尉憲景も合力あらんとて、家老矢野山城守・牧弥三郎に二百余騎を差添えて、同じく岩櫃に着陣す。越前入道斜めならず悦んで、甥弥三郎則実に家の子富澤但馬・同じく勘十郎・同じく伊賀・同じく又三郎・蜂須賀伊賀、一門には中山斎藤安芸の守・尻高左馬介・荒巻斎藤宮内衛門、その外塩谷源次郎・蟻川入道・佐藤豊後・その勢三百余人、沼田勢と合わせてハ百余騎、雁ヶ沢口へ差向けらる。大戸口へ次男斎藤四郎大輔憲春・富澤但馬(雁ヶ沢へ向かった?)・唐沢杢之助(唐沢玄播父)、一族には植栗安芸守元信、外様には中沢越後・桑原平左衛門尉・同じく大蔵(おおくら)・二ノ宮勘解由・割田新兵衛尉・同じく隼人・鹿右衛門佐・茂手木三郎右衛門・高山左近・富澤主計佐・井上金太夫・神保佐左衛門・川合善十郎・高橋三郎四郎・伊与久大五郎・荒木・小林・関・田村・一場左京進以下都合八百余人、白井勢と合わせて一千余騎。その外一ノ宮・首宮・鳥頭・岩鼓・和利宮神主。川野・片山・高山・小板橋神主らに至るまで、この度の御大事申さんとて一類を集め百余人、同年九月十五日辰の一天岩櫃を発って仙人が岩の南なる手子丸城の城へ寄せたりけり。真楽斎手の者加辺、鉄砲打掛ければ、たやすく寄せるべき様も無く猶予して見えければ、祢津・矢沢・芦田・常田の人々軍兵を率いて榛名山居鞍ヶ岳を越えて山上より真下りに喚(をめ)いて掛かりければ、斎藤案に相違して山上より攻められ、叶はずして、鞭を打って茶臼(長須)の橋の辺、郷原の十二神の森・志戸(四戸)・生(原)・梅ヶ窪に引き退く。雁ヶ沢へと向かいける人々には難所なれば、此処彼処の山々谷々に控へ居て寄せ来る敵を待ち掛けたり。幸隆父子無双の勇士にて座(いは)しければ、長野原にて御評定ありけるは、信州の大手なれども憲広入道難所を頼みて一門家老の者を以て防ぐべし、大戸口は子息四郎太夫を差向くべし、此方より大手に寄せん事詮無しとて、嫡子信綱公・三枝松土佐守五百余騎にて火打花・高間山を越えて涌水(わくみず)松尾の奥南光(なくわう)の谷へ寄せられる。三男昌幸公(武藤喜兵衛尉)は赤岩通りを暮坂峠を越えて折田仙蔵の城へ取り詰め給いける。城代佐藤将監入道・富澤加賀降人に成って人質を渡しければ、昌幸公より西窪治部・河原左京を入れ置かれけり。唐沢杢之助が女房子供を伴い八尺原にて御礼申しけり。このお猿後に玄播とぞ申しける。この由父幸隆公へ御注進あってその身は有笠山に出、取文(意味不明)□□(斎藤軍?)の様を遠見し給ひける。武山の城には一岩斎の末子の城虎丸は生年十六歳にて一族池田佐渡守重安付き参らせて勢をも出さず鳴りを静めて籠城す。かくて幸隆公は林諏訪の森に陣を居ゐありて先陣鎌原宮内少輔父子・相木市兵衛尉・小草野孫左衛門・湯本善大夫。横谷左近入道馳せ向かひ申しけるは、吾妻第一の難所なり。その上無双の城郭なりければ、力攻めには叶ひがたし。一徳斎入道父子御工夫有って諏訪の別當大学坊・雲林寺の僧を以て善導寺へ内通して和談の議を調べければ、住寺この由を越前入道へ申しければ、内々この度の企ては大戸・浦野・鎌原を退治せんまでの儀なれば、信玄公に御恨み無しとてこの議調ひ鎌原・浦野・大戸和談して、仙蔵の城御返しあって大戸・鎌原・浦野が人質斎藤へ相渡し、人々の帰陣の風聞しければ、人質をば甥の弥三郎に預け置き、沼田・白井の加勢も皆帰陣せられければ鎌原岩櫃に伺公し、入道に対面を遂げ一礼して、さて弥三郎に細々(こまごま)と一礼してその夜は弥三郎が館へ一宿し弥三郎が機嫌を伺い、私(ひそかに)に言ひけるは、貴方方多年の懇切浅からず候処に讒者(ざんしゃ)の故近年隔心(きゃくしん)に候なりと終夜酒宴し語りければ弥三郎も打ち解けたりと見て鎌原私(ひそか)に申しけるは、信玄多年入道殿に御遺恨有りければ、終には多勢を以て御誅罰有らん事踵(くびす)を廻らすべからず。されば貴殿今度の序(ついで)に返り忠し給えば当郡安堵し給はん事疑ひ無し。さ有るに於いては真田を以て忠信(注進)申さんとて懐中より熊野午王(くまのごわう)の起請文書きたるを取り出し、弥三郎に見せければ、大欲の者にて主従一族の縁を忘却して忽ち心変わりし、起請文を以て鎌原に一味して家の子家老の人々まで大半心変わりしたりけれども、海野長門守幸光・同じく能登守は如何有らんと覚束なき所に幸隆公より海野左馬允を以て密かに兄弟の許へ申されたりければ、固(もと)より御一門の事なりければ同心し給ひける。
海野兄弟は斎藤入道重恩の人なりけるに、かく心変わりはあるまじかりけるに、去る十二月晦日(つごもり)に能登守慈愛の少年の女身罷り善道寺に送らしむ。しかれども越前守大手の門に門松を立て置きければ歳末祝いする折なれば、門番の者これを見て、松の中をば通すまじと申す。この由能州に告げければ、能登守元来心剛(たけき)き者なれば、聞くより立腹し、自ら門に出て門松を引き破り、死骸を通しける。番の者この旨入道へ訟へけれども、さすが能登守なれば子細は無かりけり。されども入道心底に籠りたり。能登守も不快の事なりければ、正月二日本城に出仕して年始の礼儀を述べければ入道も杯持ち出しけり。その時能州「いかに入道殿、某は旧冬珍しき刀を求め得たり。これ御覧候へ」とて氷の如くなる刀を抜き出しければ、入道気色悪しく見えたりけるが、入道さらぬ態にて一見し、座興の体にもてなし、その座やがて退出す。それより互いに不改にて兄弟に心を付け、隔心(きゃくしん)にこそなりにけれ。隙を伺い伺い岩櫃を攻め取り武田へ忠信せんと思いけるが、時を待つ所にこの陣出来、究竟の時節と悦んで、矢沢綱隆同苗左馬允に内通して幸隆公へ返り忠せしとなり。幸隆公時日移さず出馬有るべし、我ら兄弟斎藤弥三郎同心の上は、連判の起請文を以て申すべしとて、同じ九月十五日に鳥頭の宮へ参詣と称し、首の宮別当專蔵坊・鳥頭の神主大隅太夫を語らひ、海野長門守兄弟・斎藤弥三郎・植栗安芸守・富澤但馬父子・唐沢杢之助・富澤加賀守父子・蜂須賀伊賀・浦野中務太輔連判の起請文相調(ととの)へ、矢沢薩摩守殿方へ差遣はしければ、幸隆公被見し給ひて、同年十月中旬嫡子源太左衛門信綱・武藤喜兵衛尉昌幸公・矢沢薩摩守綱隆・三枝松土佐守重貞・同苗兵部信貞・鞠子藤八郎・室賀兵武太夫義平・祢津美濃守信直・小泉・芦田の一統・海野左馬允・鎌原父子・西窪治部・同蔵千代丸・横谷左近・浦野義見斎、その勢二千五百余騎、追手搦手二手に分けてこの度雁ヶ沢口へ掛かり給はず、信綱・義平・重貞二千余騎を卒して暮坂越えに寄せられたり。これは沼田・白井の加勢を迎へんとの事なりけり。綱隆・昌幸公僅かに五百余人引率して大戸口より寄せられける。真楽斎兄弟も二百人引率し、須賀尾峠・丸屋の要害の辺に出向いて、この勢を合わせて七百余騎、三島越えをし給ひて類長ヶ峰・大竹に陣取り給う。大戸は案内者なりければ萩沢(現万木沢か?)の辺に陣取る。これは箕輪の加勢を抑へてなり。大戸但馬守は権田政重が鍛へたる矢の根二百づつ両大将へ捧げて御礼す。鍛冶湯浅対馬も矢の根十づつ進上して御礼をぞ申したりける。この鍛冶後には信玄公より御扶持を賜るなり。かくて斎藤越前入道憲広は敵襲ひ来ると聞き一門家老の人々会合評定有りて海野兄弟は心変わりと覚えたり、彼が人質取らんとて両人の妻子を取りて甥の弥三郎に預けられたり。大手番匠坂をば甥弥三郎・植栗河内守・富澤加賀・唐沢杢之助三百余騎にて固めたり。切沢口をば富澤伊予・蜂須賀伊賀・佐藤入道・有川庄左衛門・川合善十郎・塩谷源三郎二百余人にて固めける。岩鼓の出城には嫡子越前太郎・尻高源三郎・神保大炊介・割田掃部・有川入道・佐藤豊後・一場茂右衛門・同太郎左衛門尉・首藤宮内左衛門・桑原平左衛門・田沢越後・田中三郎四郎三百余人敵寄せ来るを遠見して居たりけり。居城をば海野長門守・同能登守其の子中務大輔・獅子戸入道・上白井主税介が籠り居て寄せ来る敵を待ち居たり。予め入道申されけるは、この城と申すは近国無双の名城、百万騎にても容易に寄すべき様無し。この度は籠城して敵寄せ来たらば弓鉄砲にてあしらひ、木戸を開いて戦ふべからず。さらば近国の敵退屈して隙有らん。其の時城を払って打って出、真田兄弟討ち取り会稽の恥を雪(すす)がんとて評定一決して静まり返って籠城す。大手の大将弥三郎敵方へ内通せんと思へども、四郎太夫憲春諸方の口々走(は)り廻り、下知し給ひければ其の調儀もならずして空しく日を送りける。一岩斎弥三郎を召して宣ひけるは、「敵方より寄せ来ず、静まり返って居る(は)甲府の加勢を待つらん、如何ある、その様を忍びを入れて見せよ」とありければ角田新右衛門と云ふ忍者(しのびのもの)の上手にてありければ弥三郎究竟(きゅうきょう)の折なりと悦びて細々と角田にこそ申させける。是ぞ入道運の尽きたる所なり。新右衛門大竹の陣所へ駈け入り斎藤が直筆の書状を取り出し鎌原に近づき、斯くと語る。宮内少輔綱隆公悦びてこの由を昌幸公へ申しければ昌幸公祝着斜めならず、角田を呼び出し宣ひけるは、「この度の忠信比類なき次第なり。其の方は城に帰り長門兄弟へ談合し、居城の曲輪へ火を付けよ。その時諸手より寄すべし」と合図を決め、角田に金子十両賜り「神妙なり神妙なり」とお褒めになって「一岩斎を討ち捕らば一廉知行を申し成し得させん」と申されければ、角田は悦喜限りなく、城中へ立ち帰り、弥三郎に斯くと語り、海野兄弟に示し合せて同十月十三日の夜中ばかりに入道の居館の主殿に火を懸けければ、入道大いに驚き、女房達を始めとして上を下へ返しければ、大手搦手一手にどっと押し寄せ鬨を上げければ、家の子家老の人々海野兄弟心変わりの事なりければ、弥三郎居城天狗の丸に差し置きける人々の人質を相伴ひ、人を付けて善道寺にへ隠し置き、その身は大手に立ち向かひ、木戸を開いて招き入れ、先陣矢沢・鎌原・湯本・西窪・横谷・小草野新左衛門尉と一手に成って二の門に寄せたりけるに、鎌原宮内城戸を乗り越えて郎党黒岩を伴ひ押し入りければ、一岩斎父子、弥三郎は如何(いかに)、長門守兄弟心変わりなり。余すな討ち取れと下知せられけるが、もとより弥三郎返り忠の事なりければ耳にも聞き入れず、越前入道殿目掛け、采配をふりかけ喚(をめ)掛りければ、矢沢この由を見給いて余すなとて、不動の谷の南の□場にて相戦ひ、四郎太夫太夫を討ち取り給ふ。言ひ甲斐無き弥三郎なりとて焼け崩れたる居館に帰り、腹を切らんと宣ひけるが、嫡子太郎殿出丸より帰り来て「是(これ)は勿体無き御事なり。我々防ぎ申さんに、一先越後国に落ち給ひ、景虎卿を相頼み、一度御運を開きあれかし」と云ひ捨て大長刀水車に回し、富沢藤若・秋間五郎・斎藤無理之介・佐藤半平・鹿野介五郎・浦野左門・福田久次郎・善道寺の番僧伝浦・林覚・林清御供にて、大手搦手の敵押し払ひ給ひける。今朝まで二千余ありける兵もその日の未時(ひつじどき)には二百余騎には過ぎざりけり。されども無双の城郭なりければ容易く寄すべき様も無し。此処彼処(ここかしこ)に寄せたりけれども山上より大木大石投げかけけるにより、流石の真田勢この勢ひに辟易して川向うへぞ引き退く。かくてその日も晩景に及びければ、父子一所に集まり、武山に引き籠り城虎丸と一所に越州へ落ち給はんとて、残党を集めて百余人高野平野の郷に下り給ひて見給ふ此処には真田兵部殿の手の者深井三弥・田沢主水・林新左衛門・小池太郎左衛門など落人を待ちて居たりければ叶はずしてそれより吾嬬ケ岳の麓、細尾の谷に懸かり、古座部・反下越(たんげごえ)をし給ひていなまみ山(稲包山)の麓木根宿峠を越え給ひて越後山中にぞ着き給ひける。爰(ここに)四万谷喜美野の尾の住人山田与惣兵衛と言ひし者ひし者はこの時この時病気にて出で合はざる事数代入道殿の御恩賞忘れたるに似たり。山中を越州へ落ち給ふ由を聞いて、せめて山路の見送りせんとて遅れ馳せに御跡慕ひ行きけるが、病人の事なり、山中の事なりければ、岩櫃を落ち給ひて三日の午の刻(うまのとき)ばかりに越後国魚沼郡長尾伊賀守領分嶋ヶ原に着き給ひて弁当取り出させ休息し給ひし所に追ひついてこの儀を述べ、いづくまでも御供申すとありければ、入道殿涙をはらはらと流し「数代恩賞の一門家の子郎党心変わりしける時に、その方などは外様と伝ひ、さまでの恩補(おんぶ)も行はざるに是までの志、申す言葉無し。時あらば又も相見ん事有らんや。さて武山にに残し置く城虎丸如何なりける憂き目にか逢はんずらん。行く末を万事頼む」と宣ひて御盃を賜りける。斎藤申しけるは「寿永のころ源平両家の戦に斎藤別当実盛、北国に下りしとき、故郷なりければとて錦の直垂(ひたたれ)賜り髭髪墨に染め、手塚太郎と引組(ひっくんで)んで討ち死にし、名を本朝に揚げたりける。我も元は越前の者たりけるが、この度北国に落ちける、云ひ甲斐無き有様かな」と双眼に御涙を浮べ給ひて末行の刀を山田に形見とて賜ひ、妻有(つばり)の庄にぞ落ち給ひける。
<解説>これは、岩櫃城を真田が攻めたというくだりである。岩櫃城が堅城であるが故、内応をを誘い斎藤の戦力をそいでから攻めている。最初攻めたとき和睦し、内部工作をし岩櫃城をせめ落としたと記されている。ただし、現在の定説では「斉藤氏の本拠は岩櫃城の西三キロメートル先にある岩下城ではないのか」というのが主流となっている。その根拠として、永禄六年以前の岩櫃城と記した文書がないこと。武田の文書に「岩下城鍬入れの事」という文書もあるという(管理者未確認)。それと、岩櫃城の規模が非常に大きいという事があります。一地方豪族(慶長の時代でも吾妻全体で二万石程度)の範囲をはるかに超えている。しかし、「加沢記」のこの所に、木根宿という記述がある。江戸時代に使われなくなったが、三坂峠を越え越後に向かう旧街道で古代より使われてきた道です。この街道は、坂上信州街道萩生分去で草津街道に分かれ上大戸、手子丸、兵庫、川戸そして、原町から岩櫃を抜け暮坂へ向かえば草津温泉、四万、日向見、三坂峠を抜ければ越後へ抜けられる。この街道は古代より利用され、京より東山道を来る時には三国峠より近いとされ、利用されていた。という事は、古くからこの岩櫃にこの街道を抑える城があってもおかしくない。私としては柳沢城(岩鼓の要害)が、古くからあったと感じている。さて、岩櫃城の検証に戻る。現在の遺構であるが、完全に武田式の山城という位置づけができると思います。
巻之二
羽尾入道没落の事
永禄六年十一月の事なりけり。雪厚深(こうしん)に降り積もり、人馬の通ひもなかりければ、加勢加番の者共皆々在所へ返し、手勢五六十人には過ぎざりけり。鎌原氏隙を窺(うか)ひ、羽尾を討つには(今に如(し)くは)あらじとて、甘利・祢津の手、加勢の侍同心してその勢三百余人十一月二十七日の夜半ばかりに羽尾が館へ押し寄せ、鬨(とき)をどっと揚げたりければ、入道驚き騒いで取る物も取りあへず、妻女召し連れ徒歩(かち)立ちにて夜半ばかりに用害を逃げ落ち、須賀尾峠へ懸かり落ちたりけり。雪は深し、嵐烈しくて、峠にて手端(てづま)を雪に焼き捥がれ、辛々(からがら)命助かり大戸が館にぞ落ちたりけり。岩櫃へと心掛けたりけれども、横谷も鎌原と一味してければ叶わずとぞ聞えけり。
<解説>
これにはもう一つ、坂上羽田城の伝説がある。これは誤伝であろうが、羽田城に羽尾入道が籠り、真田一味に攻められ落ちていくのであるが、須賀尾安楽寺住職に頼んで霜焼の薬を大戸氏からもらってくるように入道が頼んだ。しかし、真田方に寝返っていた大戸氏は、住職に「毒薬」を預け入道に渡した。それにより、住職は須賀尾の住人に嫌われ須賀尾に居ることができず岩井安楽寺に移動したという。羽尾入道は、鎌原を信州に追った後、真田の助力で巻き返してきた鎌原氏に敗れ、信州高井に落ちていったとの伝説もある。真田をはじめとする武田勢が西吾妻に侵攻した時、羽尾入道がどうなったか根拠となるものがないのでわからないが、羽尾入道が戦死したか信州に落ちたかでしょう。ちなみにその弟海野兄弟は、岩櫃(岩下?)の斎藤方に名前があるので、無事斎藤がもとへ合流できたのでしょう。これについては、数種類の伝承があるので真実はわからないという事だと思います。観光ではこれを、伝説として紹介するのも有かもしれません。田舎の地方史は、伝承・伝説を外してしまうと歴史がなくなってしまいます。こういう伝承・伝説の根拠を求めていくのも町教育委員会の仕事かもしれません。
吾妻郡守護并岩櫃城代の事
斎藤越前憲広入道一岩斎・嫡子同越前太郎憲宗・次男四郎太夫憲春追討の次第、幸隆公父子・三枝松土佐守・室賀山城入道・祢津宮内太夫・矢沢薩摩守会合あって幸隆公手書に連ねられける。潜龍院と申す山伏を召して一々是を記し、甲府へ注進し給いければ、信玄公喜悦浅からずして、吾妻の守護に一徳斎入道、城代には三枝松土佐守・鎌原宮内少輔・湯本善大夫、さて斎藤が一門族斎藤弥三郎・植栗主計・浦野中務太輔・富澤但馬・神保・唐沢杢之助・佐藤・有川・塩谷・川合・一場・蜂須賀・伊与久・割田・加茂・亘・鹿野・荒牧・割田・二ノ宮・桑原等の者どもは真田へお預けこれあり。本領を安堵して各々岩下の郷にぞ差し置かれける。唐沢杢之助は最前諸人に抽んで昌幸公へ忠心有りければ、本領十七貫文他所々にて知行賜りける。暫くて鎌原湯本方より弥三郎帰り忠の事両人隠密に申し定め候品追って甲州へ真田信総(のぶふさ)・室賀入道を以て申されければ一紙を以て御感状を下されける。
[群馬県史による]
斎藤越前入道逆心の企ての所各(おのおの)忠節岩櫃乗取る条誠に比類なく候。近日馬を納(い)るべく候間、弥三郎帰り忠の事申し付くべく候。心安かるべく候。委曲(ゐきょく[詳しい事は])室賀より申すべき所に候。仍って如件(くだんのごとし)。
永禄六年發亥十二月十二日
信玄在判
今度の忠節衆
この感状鎌原宮内少輔に賜りけり。明くれば永禄七年甲子正月のころ、斎藤が門族中信の族(やから)妻子を人質に出して本城に入れ置かれけるが、諸国乱世の中なれば、この城に差し置かれ候儀覚束(おぼつか)なしとて鎌原越前守を以て甲府へ注進せられければ神妙なりとて御書を下さりける。
[群馬県史による]
岩下の人質悉(ことごと)く之を執(とら)へ三枝松土佐守と談合あり、勤番せらるる之由、祝着に候。申し越され候如く畢意の人質に候之条、斎藤弥三郎に下知を加へ、きっと此の方へ召し寄すべく候。然れば最前より其の方へ召し寄すべく候。然れば最前より其の方の忠信比類なく候。猶(なほ)甘利左衛門尉を以て申すべく候。
恐々謹言
追って眼病の気故[花押に代えて]印判を用ゐ候
正月廿ニ日 信玄印判
蒲(鎌)宮内少輔殿
暫くて鎌原宮内年始の御礼の為長男筑州甲府へ参府を遂げ、熊皮五枚進上し御礼申し上げられける。湯本善大夫も白根硫黄五箱差し上げ御礼す。此の時安堵の御書をぞ下されける。
[群馬県史による]
三原に於いて渡し候先約の地斎藤横領の間、了簡に及ばず、信州海野まで替地に出だせり。此度斎藤逆心所帯没収(もっしゅ)、各先般の旨に任せ、赤川より南二百貫文の処相違なく知行到さるべく候。恐々謹言
追って熊川赤川の落合より南の儀、去る壬戌(みずのえいぬ)年頭検使相定めの如く相違有るべからず候。山の事も同前
永禄七年甲子
二月十七日 信玄在判
鎌原越前守殿
本領草津谷に於いて取り来たり候通り、羽尾領内立石・長野原等の分、先約の地合わせて百七十貫文の所相違なく知行領ぜらるべく候。追って草津の内の儀も前々の通りに候。巳上
同 信玄在判
湯本善大夫殿
海野兄弟の妻女・斎藤弥三郎妻女・富澤但馬妻子・植栗相模娘・唐沢杢之助二男お猿等の人質等甲府へ召し寄せられ、下曽根岳雲軒預けられける。斎藤弥三郎には吾妻郡の内斎藤入道蔵入地の内五分の一領川戸上村に差添へ下さりける。その外は本領安堵して居たりけり。海野兄弟は真田へお預けこれあり、信州佐久小県両郡の内在々上り地少々宛行(あてがい)へけり。猶(なほ)も斉藤城虎丸(じょうとらまる)は家臣池田佐渡守・同じく甚次郎付き随ひ・蟻川式部・山田与惣兵衛・割田下総・鹿野大介・植栗主殿介(とものすけ)無二の臣にて中山尻高与力して越後に忠信して立籠りけり。一徳(斎)入道安からず思し召して数度の合戦止むこと無し。この由謙信公聞し召して、川田伯耆守・栗林肥前守を以て出張と聞えければ、甲府へ注進有りければ、信州水内郡川中島の城主清野刑部左衛門尉甲府より曽根七郎兵衛尉を差向けられる。清野へ下されける御書有り。その文に曰く
[群馬県史による]
越後衆沼田まで出張の由に候。依って当国よりは曽根七郎兵衛立て遣はし候。早々長野原辺に着陣一徳斎指図により岩櫃へ相移らるべく候。そもそも其方事近日信濃より帰陣幾(いくばく)程もなく此の如く下知の条誠に憚(はばか)り入り候と雖(いへども)も急速(さっそく)の出陣遍に忠信たるべく候。恐々謹言。
尚々敵出張の由、有無を真田迄聞き届けらるべく候。巳上
甲子 三月十三日 信玄 在判
清野刑部左衛門尉殿
さる程に清野・曽根千余騎にて岩櫃に着陣す。武山の城へ栗林肥前守・田村新右衛門尉加勢してその勢雲霞の如く見えたりければ、永禄七年三月下旬、成田原三の原に於て合戦有りけるが、晴信公甲府を御立ち有って上州南牧余地峠を越えて箕輪に着陣と聞こえければ、武山の城へ引き籠って軍を上げて籠城す。その頃大戸浦野も箕輪にて御礼相済みける。鎌原も軽井沢駅へ使者を以て申し上げければ則御書を下さりける。
[群馬県史による]
其の方峠(かせ)ぎ故浦野忠節感じ入り候。敵地の麦作悉く刈執り、和田・天引・高山へ籠め置き、倉賀野諏訪安中の苗代薙払ひ其の上武州本庄・久□(不明)迄放火内々暫く馬を立つべく候と雖も最前よりこの度は此の如くの行(てだて)の外別条有るべからざるの旨存じ付け候。殊(こと)に民農務の時に候条来月下旬早々出張すべく、今日平原迄帰陣し候。夫(それ)に就き其の地の番勢、浦野・祢津・真田の衆申し付け候。先づ□番として常田新六郎・小草野孫左衛門・浦野左馬允以下相移り候。委曲甘利申すべく候。恐々謹言。
永禄七年
甲子 五月十七日 信玄在判
鎌原宮内少輔殿
かくて武山の加勢と一井斎と一手に成りて岩櫃を責むるとて評議区々の由幸隆公聞き給ひて、最前箕輪へ白倉武兵衛を以て申されけるが、加勢をば附けられたり。加勢に安中越前入道三河衆三百余騎五月下旬着陣す。猶此の事謙信公聞き給ひて、柴田右衛門尉・藤田能登守二千余騎を差添え、木の根峠越え三国峠強清水(こわしみず)の辺に着陣すと聞こえければ、後番の真田信綱手勢五百余騎を率し先陣川原左京・丸山土佐守に二百余騎相添へ朽葉四方の大旗に六文銭の紋書を真先に進ませ、岩櫃の城に入らずして沢渡伊賀野山に陣取り給ひける。祢津元直は五百余騎を従へて先陣家の子子田沢兵庫助・加沢出羽・別符若狭、後陣は嫡子利直二百余騎にて水林与七郎・藤岡左中・白石兵庫を差添へ、都合七百余騎岩櫃に着陣す。□(先)番勢幸隆公の勢、地衆を合わせ三千余騎、雲霞の如く集まりて寄せ来る敵を待ち給いける。かかりける所に池田佐渡守父子降人となって出て、主君斎藤を盛り立て申すが為只今迄敵となり候なり。城虎丸御助け有らんに於いては無二の忠信仕らんと植栗を以て幸隆御父子へ申されければ、子細無しとて人質を受け取り和議し給ひける。かくて信州寄せ手の人々清野・曽根の両将も帰陣せられければ、その年は静謐(せいひつ)にて暮にけり。
<解説>
このくだりは、岩櫃城を落とした武田氏の戦後処理を記したのと、斉藤氏残党が中之条町の武山に籠り岩櫃城を奪還せんとしたくだりである。斉藤氏残党が、武山城を拠点に巻き返しを企てていたのは、上杉方と武田方の境界の緩衝地帯で、領地としてそこが空白地となっていたためとする説がある(飯森康広氏説「戦国期の上野の城・紛争と地域変容 岩田書院刊」)。それには諸説あると思うが、東吾妻町教育委員会ではまた少し違う見解を模索しているようである。ここに載っている五百騎とか三百騎とか三千騎などは、騎ではなく人に換算する方が妥当だと思う。ここで注目すべきは、武山方が上杉の援軍を要請して謙信が派兵をしていることである。これにより、武田方との兵力差は拮抗することになる。通常城攻めの兵力は、籠城兵の三倍は必要であるといわれている。この状態では、城攻めは不可能なことがわかる。幸隆(幸綱)が武山勢と和睦したのも、うなずける根拠となるのではないか。和睦とともに、幸隆(幸綱)が懐柔工作を始めている。これは、謀略の得意な真田の真骨頂であると思います。狙われたのは、斉藤氏重臣池田佐渡守・甚次郎親子である。最初、「斉藤城子丸の助命と引き換えに降伏をする」という事で交渉を始めたが、最後には寝返りという結果になってしまう。しかし、この佐渡守・甚次郎親子は本領安堵と信州真田原之郷に新領を賜り、昌幸・信之と重臣として使えることになる。
<参考文献:詳しくは下の「戦国期上野の城・紛争と地域変容 飯森康広氏著」を参考にしてください>
武山合戦斉藤越前太郎并城虎丸兄弟最期の事
斉藤越前太郎憲宗は去る年北国へ落ちて長尾伊賀守を相頼み、魚沼郡早川の郷に居住し給ひけるが、一度故郷に本意せんと企(くはた)て、長尾・栗林両家少々加勢賜り、諸浪人を招き集めて五百余騎引率、永禄八(1565)年十月下旬武山に着いて舎弟一所になって一井斎(長尾憲景?)の加勢を請ひ、中山・尻高・小川・赤松可遊斎合力(かふりょく)して其の勢二千余騎にて同年□□月旗を揚げたり。岩櫃には思し召し寄らざる事なりければ、上を下へと返しけるが、幸隆(幸綱)公・信綱公兄弟(親子?)武略の武兵(ぶひゃう)なりければ物ともし給はず、城を堅く守らせて、富沢但馬入道・唐沢杢之助・植栗安芸守を以て武山へ申されけるは、太郎殿近年北国にましますの由、内々晴信公へ申し成し、一度本意を遂げさせ申す上、当城に残る御一族にも申し候を、去年より村上と相戦ひ、本国を没落し、当国長野の庄に浪人して我が身を顧みず候なり。此の度和談相調へ、甲州へ申しなし、矢澤殿婿に取り結び、本所に返し申さんと細々と申されければ、太郎誠と心得て左右(さう)無く和談を遂げ、加勢の武士返し給ひて互に人質取り交わしければ、池田佐渡守重安を招いて幸隆(幸綱)公迎せられけるは「斉藤の家の子郎党重恩の面々残らず心変わり有りけるに、貴方父子今年に至まで彼の末子を守立てけるこそ武士の本意なり。されども斉藤逆臣に付き、晴信公御憤(おいきどお)り深ければ子孫終に御誅罰有らん事疑ひなし。貴方は元来楠木正成の末孫たり。随世の習ひなりければ斉藤の下に住み給ふことなり。我に同心有って甲府へ忠信の臣になり給へかし。さらば領地長く相違無きの旨信玄公御証文を申し下し参らせん」と申されければ、池田同心なり。則ち甲府へ此旨注進有りければ、池田安堵の御証文を下されける。
其の方今日まで武山城に籠もり斉藤守り立つるの旨、誠に比類無き心底感じ入り候。然 れば此の度真田を以て当家に忠信有るべきの旨、神妙の至りに候。彼の地本意に付いて は、本領山田郷百五十貫右此(かく)の如く宛て行ふべく、猶(なほ)戦功により御重 恩有るべきの旨仰せ出さるる者也。仍って件の如し。
甘利左衛門之を奉ず
永禄八年乙丑(きのとうし)十一月十日
池田佐渡守殿
さる程に池田父子武山を引払ひ、岩櫃に参りければ、斉藤兄弟力無く、白井沼田の加勢を請ひ、有無の合戦遂ぐべしとて思ひ立ち給ひける。この由一徳斎入道聞き給ひて、時日を移さず鎌原・湯本・西窪。横谷・植栗・大戸・浦野・池田・富沢・蜂須賀を先陣に、先駆けとして、自ら三百余騎引率して黒糸威しの鎧、鍬形打ったる兜を着し、、三寸五寸の刀を佩き、十文字の鑓堤(ひっさげ)、荒井黒と名付けたる名馬に白覆輪の鞍を置き、丸山・春原・川原・矢野・小草野新三郎・上原・座村の宮下・山越・深井・原・石田・髙井・塩野・河合・山岡・富沢・一場・高山・桑原・中沢等、前後を是を囲んで簑原の此方(こなた)なる仙蔵の要害に駆け上り、軍(いくさ)の下知をし給いけり。斉藤兄弟も城を払って六百余騎、五反田の台に押し寄せ相戦ふ。かかりける所に西窪治部左衛門先陣に駒駈け出し、斉藤が先陣秋閒備前・大野新三と相戦ひ、秋閒を討取り迎へて首を掻きければ早川源蔵百余人にて西窪を取り籠め終いに西窪討たれにけり。蜂須賀伊賀此の由を見てかかりければ是も同じく討たれにけり。真田此の由を見給へて自身鑓提(さ)げ斉藤をを目に懸け給ひてかかり給へければ、斉藤此の勢ひに辟易して前後しどろに見えければ、真田の家の子春原・川原・矢野・丸山・山越・鎌原・湯本の人々抜き連れて喚いてかかりければ、味方も百五十余騎討たれにけり。日も夕陽(せきやう)に傾きければ斉藤貝吹きて城山に引き入りける。寄り手の人々は明くるを遅しと夜中より武山取り巻き、竹束を付けて山上とも言はず喚いて攻めたりける程に、唐沢杢之助一の木戸にて討死にす。湯本善大夫此の由を見て余さじと討ち取りければ憲宗叶叶はずして是までなりとて腹十文字に掻き切って三十八を最期として失せ給ひける。抑(そもそも)此城と申すは岩石岨立ちて瞼岨(けんそ)なる事北国倶利迦羅が城と申すとも是に勝るべしや。斉藤が運命尽きたる瑞相にはようがいの嶮岨なるを頼みて昨日軍兵残らず城に入れ籠城したりし故なりけり。城虎丸は本城北の天狗の峰に駆け上り給ひければ敵隙間なくかかりければ、天狗岩より飛び落ち給日て終に岩石に当たり、微塵に成って失せ給ひける。その外付き従ひたる女房達此処彼処の岩の下に落ち重なって一人も残らず失せにける。其の骸骨今に有りとなり。かくて武山の城には池田佐渡守・河原左京・鎌原・湯本を籠め置き、この由甲府へ注進有ってその身は岩櫃に住み給ふなり。翌年武山にて討死の人々に御感状領地安堵の御証文を下されける。
信玄公御伴此処なり
父治部嶽山に於て戦死、寔(まこと)に忠信の至り感じ入り候。然れば知行等の事異議 なく相談すべきものなり。仍って件の如し。
永禄九(1566)年丙寅(ひのえとら)三月晦日
西窪蔵千世殿
信玄御伴此処に在るなり
父杢之助嶽山一の木戸に於いて討死、忠節の程感じ入り候。然れば知行の事相違なく相 談せらるべきものなり。仍って件の如し。
永禄九(1566)年丙寅(ひのえとら)三月晦日 唐沢お猿殿
蜂須賀伊賀討死に付き、息舎人へ同前の証文下されける。
去年十一月嶽山一の木戸口辺に於て強敵早川源蔵討ち取り、その身も数ヶ所創負(てお い)ひ、晴れの勝負則真田所より注進せしめ候。比類無き次第に候。依之(よって)羽 尾領の内林村に於て二十貫文の所加増せしめ候。猶戦功により重恩を加ふべき者なり。 仍って件の如し。
永禄九(1566)年丙寅(ひのえとら)三月晦日 信玄在伴
湯本善大夫殿
富沢六郎三郎同前、此の者十兵衛父なり。
<解説>
永禄八(1565)年乙丑(きのとうし)、斉藤氏旧勢力が隆起した。永禄六(1563)年癸亥(みずのとい)十一月岩櫃城(岩下城?)を落とされて実質、斉藤氏は没落した。斉藤憲広と嫡男太郎憲宗は、越後に逃れ再起の機会を狙っていた。憲広は失意の内に越後で亡くなり嫡男太郎憲宗、次男憲春、末子城虎丸の三兄弟が武山を本拠に岩櫃城奪還を狙っていた。武山周辺は、岩櫃を落とされていたが空白地帯となっていたのでは無いか(群馬県埋蔵文化財調査事業団 飯盛康広氏説)。まだ真田の統治が及ばない地点に於いて、斉藤方旧勢力(浪人衆)、越後の加勢と中山尻高の同族衆、沼田衆、白井衆の力を借りて蜂起した。此の勢力は侮りがたく、真田幸綱(幸隆)と加勢の武田方の勢力では決戦は難しく、幸綱の謀略によりいったん和談となる。斉藤方の加勢の衆を一旦引き揚げさせてから、すぐに決戦を挑んでいる。幸綱のしたたかさが伺える事象であると、言えると思う。今の嵩山の地形を見ると、要害部分には水が無い。恐らく親都神社あたりが砦の最前線で、そこを破られれば最早ジリ貧であったと思う。親都神社の下の方に、陣平という地名が残り真田幸綱が陣を張った所と伝わる。これを考えると、今の親都神社あたりに斉藤方は陣を構え、武田勢を迎え撃つのが正攻法と考えられる。最初に戦端を開いたのが、簑原と「加沢記」には記されている。この場所は、現在の東京電力中之条送電所のある場所周辺です。ここで決戦をして、敗れた斉藤方は武山に撤退して籠城戦をしたのでしょう。しかし、加勢を帰国させて、兵力は斉藤方が不利なのは事実だった事だろう。武田氏は同時期、箕郷の箕輪城攻め落としている。籠城戦は、後詰めの兵が無いとこの時期には負けが確定している。山城というのは水が無いので、麓の要害を占拠されて山上に籠もっても持って10日ぐらいしか持たない可能性がある。後詰めを期待できない斉藤方の旧勢力は、幸綱の謀略によってジリ貧となっていった。何れにしても、武田方が東と西から上州に攻め入っていたので武田に敵対しても、勝ち目は無かったでしょう。
沼田万鬼斎嫡子弥七郎殿御中不和の事附沼田滅亡の事
一、顕泰公天文年中(1532~1554年)に利根郡小川の温泉に浴湯し給ひて同郡追貝村の名主、金子の何某が娘を寵愛の余りその名を「湯呑(ゆのみ)」と名付け給ひて仮初に召し使いけるが、その腹に御子一人誕生し給ひけり。御名を「八郎殿」と申しけり。御傅に彼の母公の叔父追貝村の名主金子新左衛門(美濃守)と言ひし者と三橋甚太郎と言ひし士(さむらい)を刺し添へて、二ノ丸にぞ御座(おはしま)しける。八郎殿十一歳の御時川波(川場)郷吉祥寺へ手習いの為登山ましましてけり。器量世に越へ、大兵にましましけるによりて十五歳にて元服し給ふ。沼田平八郎平景義と名乗り給ひけり。その頃安田とて兵法(ひゃうほう)の名人当国に来たりけるを、沼田に招き寄せ給ひて師に御頼み有りて兵法を倣い給ふに、御力万人に勝れ早き事世に並び無ければ、兵法の名誉魔利支天の尊(来)かと世の人申しけり。時に永禄九(1566)年安田にかへり起請(起請文)書かせ、景義も同日に血判を以て安田方へ取り遣はし給ひける。御起請文に永禄九(1566)丙寅(ひのえとら)年閏八月五日平八郎景義と有りける。在家に古き侍筋の持ちたるを披見したりければ世の人申し伝へたるも実なりと感じけり。平八殿を万鬼斎御寵愛の余りに金子新左衛門を美濃守泰清と官途(くわんど)し知行永楽八十貫文を賜り弥七郎殿の家臣に付け給ひ、代々の老臣御一族の和田掃部介と同役付け給ひけり。是ぞ沼田の滅亡の基なり諸人是を悲しめり。さて景義の御母公に思されけるは、平八郎殿を沼田総領主になさばやと明け暮れ御舎兄(ごしゃきゃう)金子美濃守と御内談有って、謀を以て弥七郎殿を失ひ奉るべしとて、折々万鬼斎へ諫言し、御中不和にならせ給ひけり。此の上は和田掃部を失ひ思ひの儘に為さんとてその頃弥七郎殿の御奥を御曲輪の御前と申しけるが、彼の御前と和田と密通の由、天然と申し成しければ、万鬼斎安からず思召し、和田を川場へ召されければ、和田も流石なりけれども、世に申し開き難くや思ひけん、永禄十一(1568)年秋頃三十一にして上沼田の館を忍び出て、高野山に入りて花の笄(こうがい)剃りこぼし、実を墨染と成してけり。この由川場へ聞こえけば平八郎殿を始め、母公金子美濃、本望を遂げたりとて明くれば永禄十二(1569)巳の正月五日に万鬼斎より吉祥寺の住僧に久屋斉藤三河太郎入道が裔孫(えいそん)塩野井又市郎相副(あいそ)へられ、弥七郎へ仰せ遣はされけり。その御書札に曰く
近年不幸の旨、和田が為業なり。今以て後悔其の益なし。
掃部在所退去の上は子細なし。
早く我が館へ参向待つ所なり。委曲は塩野井又七郎申し述ぶべく候。謹言
正月五日 万鬼斎入道
顕泰在判
沼田弥七郎殿とぞ遊ばさるける。此の状をを塩野井受け取り早馬にて同日午刻(うしのこく 正午)ばかりに倉内の城に来たり、恩田越前守・金子美濃守・岡谷平六左衛門を以て申し上げければ弥七郎殿は吉祥寺・又市郎に御対面有って彼の御書礼を三度頂戴し給ひて謹んで拝見有って斜めならず御悦び、早速御返答に及び明日出仕仕るべしとて塩野井に杯を賜り、泰重が打ったる御刀を賜りければ、又市郎も大事の御使をし済ましたりと思ひ、金子と小頷(こうなづ)きして川場へぞ帰りけり。弥七郎殿此の事夢にも知り召さず、明くるを遅しと御共触れ有って、僅かに五十人ばかり御供廻りにて、騎馬の御供には長谷平六左衛門・下ノ源次郎ばかりなり。永禄十二年正月三日の早旦に倉内の城を御立ちありて下川場の館へ参られける。万鬼斎予て用意のの事なりければ、御迎への為星野図書介を生科の里まで差し遣はされけり。図書介も遙かに控へて下馬して待ち奉りけるが、弥七郎殿も星野を御覧有って馬より下り給ひて、珍しの図書介、讒者の故に此の二三年父の御顔を拝し奉らず、空しく年月を過ごしけるが、此の度恩赦に頂き今日御舘へ参る事編に仏神の御加護と有り難く嬉しく思ふは如何にとて弁当の酒取り出させ給ひて三献干し給ひて星野にぞ賜りけり。それより御舘へ入らせ給ひければ、御次の間廊下の内に抜き連れて待ちかけたるお夢にも知ろし召さざりしかば、袴肩衣を召されて出で給ふほ唯一一太刀にて討ち奉りけり。無残なるかな御年三十六にして継母の讒に依って討たれさせ給ふ。昔が今に至るまで継嗣継母の御事は心意(得)有るべき事なりと諸人是を思ひけり。其の時何者かしたりけん一首の狂歌を詠みて川場の御舘の辺、倉内の城大手の橋の際に建て足りけり。
罪科(つみとが)の報いも知らず蚕飼(こがい)して蚕蛾(ひひる)
[ヒヒルは蚕の蛾の事]
蛹(さなぎ)になるは秋安[顕泰]とぞ書き付けたり。
<解説>
この記述は、沼田騒動の事です。沼田顕泰が「沼田万鬼斎」として、川場に屋敷を建てて隠居した。沼田氏の家督は沼田弥七郎憲泰が継ぎ、倉内の城に入った。しかし顕泰の晩年、愛妾「ゆのみ」に男子ができ、ゆのみと其の叔父金子美濃守が沼田の当主をその子「平八郎景義」に継がせたいと「顕泰」をだまし、謀略を持って弥七郎憲泰を討ったと言う下りです。「加沢記」は元々、真田氏を持ち上げて記す書物であったので、真田昌幸によってだまし討ちに遭い最期を迎えた沼田平八郎平景義を悪く書かなくては真田氏の正当性が担保できません。沼田の当主憲泰と前当主顕泰の抗争に対して、顕泰方を悪者にしなくては平八郎景義をだまし討ちにした真田は、卑怯者という事になってしまいます。沼田顕泰と平八郎景義を悪者にすることで、真田昌幸が沼田平八郎平景義を討った事の正当性を担保した記述だと思います。
さて、実際の背景を考えてみたい。長尾景虎(上杉謙信)、越山(関東遠征)での着到状で「関東幕注文」がありその中に記されている沼田衆の筆頭は「沼田顕泰」でしょう。つまり、顕泰は上杉方と言うことが言えると思います。沼田は、越山の時の重要な地点となっていました。しかし、憲泰の時には越後の武将が城番として沼田に在城していました。つまり、憲泰が沼田に対して全権を持っていなかったのが推測されます。これに不満を持っていた憲泰が、「小田原北条氏」に寝返ろうとしていたのでは無いか。そうするとこの一連の騒動は、北条方の「沼田弥七郎憲泰」と上杉方の「沼田万鬼斎」の沼田氏家中の争いでは無いかと考えられる。沼田氏は元々箕輪の長野業政との関係が深く、長野業政は上杉謙信方として最後まで忠誠を尽くしていた。それに厩橋城の北城(きたじょう)高広動向など見ると、高広は最後になると「小田原北条氏」に与した。こんな一連の流れから、沼田氏の内紛として起こった出来事では無いかと推測される出来事です。この項に永禄十二年と言う年代が出てくる。岩櫃城の落城が永禄六年、武山の合戦が永禄七年、そして箕輪城が武田に落とされたのが永禄九年、白井城が武田のものになったのが永禄三年です。その後白井に、長尾憲景が復活する。この長尾憲景は、上杉に従ったり北条に従ったりしたが武田に従ったことは内容である。この永禄九年というのが、長尾憲景が北条方として白井城の復活した年代では無いのかという憶測も立つ。この一連の騒動は、この頃の複雑な時代背景から起こされたことでは無いのかという思いは、私だけの思いでしょうか。
川場合戦の事
この事倉内に隠れなし。御供の人々討たれ、残りたるは倉内に立ち帰り始終を申しければ、恩田越前守を始め以ての外驚き、早鐘を鳴らしければ、下沼田豊前守・発知刑部太輔・久屋左馬允・岡谷平内・石墨兵庫助・宇楚井孫八・山名信濃守・小川可遊斎・名胡桃の鈴木主水・発知図書・萩野但馬・師大助・高野車・小屋弥惣・高野但馬・真下但馬・深沢・小野・吉野・小保方・戸部・戸口・七五三木(しめぎ)・増田・高橋・靏淵(つるぶち)星野・吉沢・桑原・小林・中嶋・金井・小池・小淵・青木・杉本・後閑・町田・小野・津久井この人々を先として都合一千三百余人駿馬に策打って同日晩景に馳せ集まり、軍評定しきりなり。翌七日の辰の一点に川場の舘に押し寄せたり。川場より注進に帰り参りける吉沢と言ひし商人に侍一人御添へあって御曲輪の御嫁より前橋へ御文を遣わされければ、弥五郞(北条高広)殿安からず思され、手勢二百余騎大胡殿をその日の大将に定めて翌八日の未の刻(午後一時から三時)ばかり前橋を打立って沼須へこそ着陣す。万鬼斎御父子予て思はれけるは、弥七郎殿生害し給はば一族家老の者までも景義へ思ひ附かん事疑ひなし。金子は城に控へたりければ一軍にも及ぶまじ。若し弥五郞殿より遺恨軍兵を遣はし給ふ事あらば永井坂要害にて待ち受くれば何万騎にて来るとも物の数には思はず、定めて美濃が来るらめとて秋塚の五六の岩の上に物見を出して待ち給ひければ、案に相違して発知・久屋・山名の人々を先として沼田相伝の左巴の大旗真先に進ませ、喚(をめ)き叫んで押し寄せたり。物見の侍舘へこの由申しければ、平八郎殿安からず思して唐櫃の蓋を開けて緋縅の鎧に鍬形打たる兜を取り出させ、泰重が打たる四尺八寸の沼田打ちの太刀二尺七寸の打刀(うちがたな)、九寸五分の鎧通し十文字に横たへ、七寸(しちき)余りの旗谷黒云ふ馬に、御前祖同安齋自作の銀覆輪の鞍置かせ、三尺五寸の大長太刀(おおながたち)打ち傾げ、殿は万鬼斎黒糸威しの鎧を召され、白布にて鉢巻きして長身の手鑓打ち傾げ、葦毛の馬に朱鞍を置かせ打ち乗り、手勢僅か三百余人前後に是を囲ませ、横塚の原へぞ出向き給ひけり。万鬼斎景義に向かって云ひけるは、敵大勢なれば掛合ひの軍叶ひがたし。表裏を以て打つべしとて三百人を三手に分け、景義に百余人分け虚空蔵山に□□□百余人の兵をば塩野井又一郎に相添へ生品の武尊(ほたか)の森の内に隠し置き、自ら百余人を引率して鎧の上に茜染めの紬のきるものを着して中々一軍にも及ぶべき様は見えざりけり。寄手の先陣川田城主山名信濃守嫡子小四郎・上川田城主発知図書介・萩野対馬守・相随ふ者には高野車・小屋弥惣・師大助・下の十左衛門・関上甚介・生方半左衛門・神保大蔵(おおくら)・中島主税介・戸部左馬允・中村式部・高橋右近介・深津次郎兵衛三百余人、真先に進んでまっしぐらに成って万鬼斎へ討って懸かる。後陣の勢は愛宕山に控えて見物す。そのころ万鬼斎七十に渡らせ給ひけるが、大音声に仰せけるは、「先陣に懸けたる旗の紋を見るに、白旗に根笹は山名と見えたり。赤地にカヤデを書きたるは発知図書と見えたり。重代の家人又は総領の家に向かって弓を引く事天罰遁れがたし。早く兜を脱ぎ旗を巻き降人(かうにん)に来れしか」と宣ける。流石大強(剛)の人なりけれども、相伝の大将顕泰にてましませば弓鉄砲を打ち掛くべき様もも無く猶予して、宛ら進む気色なし。後陣に控へたる発知・岡谷(おかのや)・久屋(くや)が勢、横合に掛からんとて五百余人にて喚(わめ)いて掛かりければ、森の内なる塩野井一陣に駒駆け出し、久屋左馬允が控えたる陣の中へぞ駆け入ったる。もとより一族の事なりければ互ひに恥ぢてや戦ひけん、切先より火花を散らし鎬(しのぎ)を削り鍔(つば)を割り、未の刻(午後一時から三時)ばかりより申の下(刻 午後四時から五時)まで、ひらりくるりと戦ひける。馬上の太刀打ち是ぞ軍の見物と鳴りを静めて控へたり。互に手利きの名人なれば手も負はずして相引きに引いてぞ本陣へ帰りけり。俄(にわ)かに大雪降り来たり諸勢凍え人馬も竦(すく)みければ互に引いてその日の軍は止みにけり。終夜(よもすがら)雪深く翌八日も終日(ひねもす)雪降りければ軍成らずして空しく愛宕山の辺(ほと)りに小屋を掛け控へけり。さて金子美濃守は何とか思案したりけん、七日の日の暮方より風気となりて宿所に引き籠りてこの評定に出で合はざりけり、軍散って聞えしに一心に愛宕をを祈念してぞ居たるとこそ聞こえし。仰金子と云う者名主職の時より常に愛宕を念じけるが、顕泰公へ召し出だされては尚以て怠る事なし。天文年中(1532から1554年)に倉内の鬼門横塚と云ふ所に愛宕を建立したりける其の本尊今の世に海応山金剛院に安置し給ふなり。
<解説>
沼田顕泰が、晩年ゆのみを寵愛して末子平八郎を設ける。家督は、沼田弥七郎憲泰に譲っていて顕泰は隠居して万鬼斎(ばんきさい)を名乗る。しかし晩年に出来た平八郎景義に家督を継がしたいと思い、憲泰をだまし討ちにした。万鬼斎はこれで家督は平八郎に来ると思っていたのだが、沼田の重臣達は厩橋城の北条高広に援軍を要請して万鬼斎に敵対する。これは、万鬼斎にとって想定外の出来事であったでしょう。そして、川場にて沼田の重臣と、沼田万鬼斎の合戦となる。この合戦の兵力は、万鬼斎不利の状況であったが大雪の為、決着は付かなかった。しかし、ゆのみの叔父金子美濃守も倉内城にあってだんまりを決め込む。倉内城内の評定は、万鬼斎と決戦と意を決したので美濃守も動けなかったのでしょう。この事などが後の時代、真田昌幸に嫌われる事となったのかも知れません。しかし、大勢は万鬼斎には無く敗れる事になる。この下りでは、雪により決着が着かなかったようです。しかし、大義は万鬼斎には無く最後には川場を落ち、会津に逃げていったようです。この頃の国人領主の御家騒動は、どの勢力に附くかが大きな原因となっていたのでは無いでしょうか。案外、上杉と後北条の勢力争いの一環だったのでは無いでしょうか。
